RAGとは? 生成AIチャットボットの精度向上の仕組みについて解説
2024.10.21
Contents
お役立ちコンテンツ
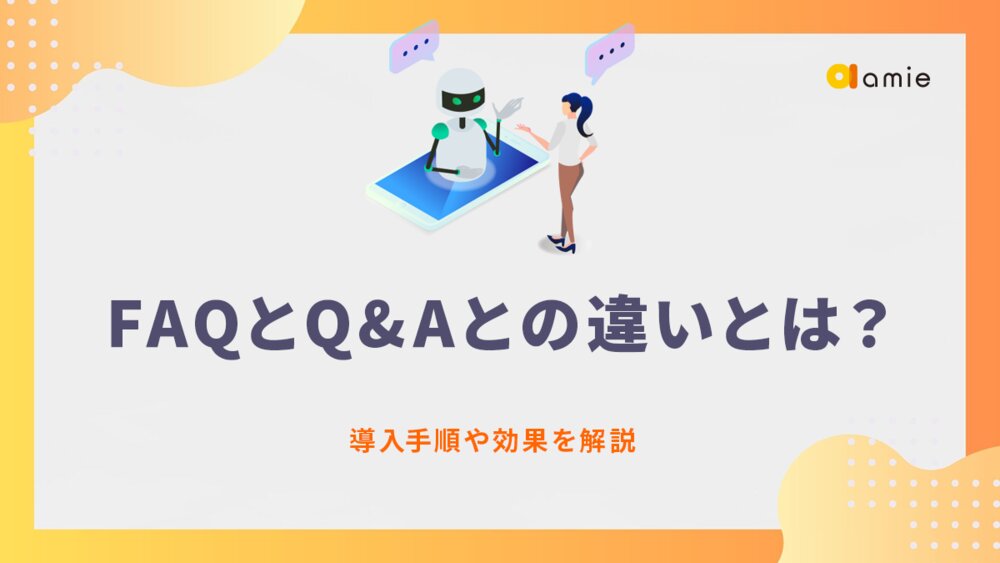
ECサイトや企業サイトには、「よくある質問(FAQ)」というぺージが設けられていることが一般的です。FAQには顧客から寄せられる機会の多い質問と回答がまとまっているため、顧客は自ら疑問や不明点を解消できます。
一方、Q&Aには実際に寄せられた質問だけでなく、尋ねられる可能性が高い質問も掲載されているため、情報量が多くなる傾向があります。両者の違いを理解して、上手に使い分けましょう。
本記事ではFAQとQ&Aの定義や特徴、それぞれのメリットとデメリットなどについて解説します。
目次

FAQはFrequently Asked Questionsの頭文字を取った単語であり、日本語では「よくある質問」と訳されます。寄せられることの多い質問に対して、標準的な回答を集めたものがFAQです。
FAQと同じように扱われる傾向にあるのがQ&Aです。Q&AはQuestionand Answerの略であり、「質問と回答」と訳されます。Q&Aも特定の質問に対して一対一の回答を行う形式です。
ユーザーはFAQやQ&Aの中から自分の疑問に近い質問を選ぶことで、不明点を自力で解消できます。

FAQとQ&Aはどちらも質問と回答がセットになっているコンテンツです。しかし、その内容には違いがあります。
FAQは実際に寄せられた質問の中でも、多くの人に共通する質問に対してその回答をまとめたものです。Webサイトやサービスをスムーズに利用してもらうために、ユーザーが最初に抱きやすい疑問の解消を目的としています。
一方、Q&Aは実際に寄せられた質問だけでなく、今後尋ねられる可能性が高い質問も先回りして回答掲載しています。そのため、FAQよりも情報量が多くなる傾向があり、より個々の疑問に対応可能です。
FAQはより実用的で利便性が高いツール、Q&Aはより詳細な情報を提供できるツールといえるでしょう。どちらが優れているということはなく、目的に応じた使い分けが重要です。

FAQとQ&Aは活用シーンが異なります。ここではそれぞれの代表的な活用シーンについて解説します。
FAQはサイトのヘルプやサポートに用いられるのが一般的です。具体的には次のような活用シーンが挙げられます。
対顧客用のFAQ
対従業員用のFAQ
対コールセンター用のFAQ
対顧客用のFAQとは、顧客から寄せられる質問とそれに対する企業からの回答をまとめたコンテンツです。例えば自社の商品やサービスに興味がある顧客に対して、商品の仕様やサービスの内容などをFAQとしてWebサイトに掲載します。
対従業員用のFAQは、自社の従業員に向けたFAQです。業務フローやツールの使用方法など、業務を進める上で発生する質問と回答がまとめられており、社内FAQとも呼ばれています。
一般的に対従業員用のFAQは社内のみで使用され、外部に公開されることはありません。対従業員用のFAQを導入することで、従業員自ら疑問や課題を解消できるでしょう。
対コールセンター用のFAQも自社の従業員に向けたFAQです。しかし、前述した対従業員用のFAQと異なり、対コールセンター用のFAQを使用するのは顧客対応を担当する従業員のみです。対コールセンター用のFAQには、顧客から頻繁に寄せられる質問とその回答が整理されています。これを活用することで、担当者は問い合わせに対してよりスムーズかつ的確な対応が可能になり、顧客満足度向上が期待できます。
Q&Aの活用が適しているのが、商品やサービスのマニュアルです。Q&Aは、顧客から寄せられる質問を企業が想定して回答を用意したものです。FAQのようによくある質問だけを集めているわけではなく、さまざまな情報が網羅されています。
商品やサービスの利用に当たって疑問が生じた場合でも、Q&Aを活用すれば、リアルタイムに必要な情報を見つけられるでしょう。
FAQを導入する際は、メリットとデメリットを把握しておきましょう。ここではFAQのメリット、デメリットを解説します。
FAQのメリットは主に次の通りです。
FAQによって企業にもたらされるメリットの一つが、問い合わせ件数の削減です。従来の問い合わせ対応では、顧客や従業員から質問があった場合、担当者が個別に回答する必要がありました。しかし、これでは担当者の負担が増え、主要な業務に注力できなくなる可能性があります。
一方、FAQを導入すれば、顧客や従業員は自ら回答を探し出せるため、問い合わせ件数の減少につながります。結果、対応効率が向上し、業務効率化などのメリットも得られるでしょう。
FAQを活用すれば、24時間365日いつでも顧客サポートが可能になります。
担当者が個別に問い合わせに対応する場合、基本的に顧客は営業時間内に問い合わせることになります。土日や夜間のサポートも行うためには、追加で従業員を雇ったり、割増賃金を支払ったりすることになるでしょう。
しかしFAQを導入すれば、担当者が不在であっても顧客の質問に対応でき、顧客はリアルタイムで必要な情報を得られるようになります。
顧客満足度はリピーター獲得や新規顧客獲得には欠かせない指標です。顧客満足度が高ければ、売り上げ増加も期待できます。
顧客満足度を高める上でもFAQは効果的です。FAQが導入されていない場合、顧客は以下のような理由でストレスを感じることがあります。
一方、FAQを導入すれば顧客は待ち時間なく自分の悩みや疑問点を解消可能です。
FAQを導入することで、ナレッジの蓄積も期待できます。
企業によっては、特定の業務を決まった従業員のみが担当する「属人化」が課題となることがあります。このような状況では、担当者不在時の対応が難しく、業務効率の低下が懸念されるでしょう。しかし、業務の手順や対応方法をFAQとして整理することで、誰もが必要な情報を得られるようになり、適切な対応が可能になります。
さらに、FAQによるナレッジの蓄積は新人教育にも有効です。新人教育の資料としてFAQを活用することで、業務の適切な手順を伝えられ、より効率的な教育ができます。
自社の商品やサービスを改善するアイデアとしてもFAQは有効です。例えばよく閲覧されている質問と回答を分析することで、どのようなニーズを顧客が抱えているのか判断できます。FAQから分かった顧客のニーズに基づいて商品やサービスを改善すれば、より顧客に寄り添った商品、サービスを提供できるでしょう。
FAQには、SEOが期待できるというメリットもあります。FAQへのアクセスが増加すればサイト全体の閲覧数が増加し、顧客がFAQを探すためにサイトを回遊すれば評価も高まります。その結果、検索結果が上位表示されやすくなり、新規顧客の流入が期待できるでしょう。
FAQのデメリットは主に次の通りです。
一般的に、FAQを導入するためには、専用のシステムを導入する必要があります。そのため、システム導入に当たり一定のコストが発生します。FAQシステム導入の際にかかる費用は一般的に次の通りです。
顧客のニーズは多様化しているため、顧客一人ひとりが求めている情報は異なります。しかし、FAQは多くの顧客から寄せられるであろう質問と回答を掲載したものであり、一般的な内容のみに対応しています。顧客それぞれの悩みに対応する、パーソナライズされた質問と回答の設定は難しいでしょう。
FAQシステムの導入・運用にはリソースが必要です。導入時には、掲載する情報の収集や回答の設定といった複数の工程が求められ、導入後は情報を定期的に更新する必要があります。古い情報を掲載したままにしていると、回答の精度が低下し、顧客満足度も低下する可能性があります。情報が多くなれば、更新にかかる手間や時間も増えるでしょう。
FAQにメリット、デメリットがあるようにQ&Aにもメリット、デメリットがあります。ここではQ&Aのメリット、デメリットを解説します。
Q&Aは、寄せられた質問や想定される質問と回答を網羅的にまとめているものです。そのため、Q&Aは顧客それぞれが抱えている細かい質問にも対応できるのがQ&Aのメリットです。
FAQは網羅的に質問と回答をまとめるため、掲載する質問と回答の数も膨大になります。Q&A作成に多くの社内リソースが必要となることはデメリットといえるでしょう。またQ&Aはあくまでも顧客から寄せられる可能性の高い質問を載せているため、掲載する内容は担当者に依存してしまう傾向があります。
FAQとQ&Aを効果的に活用するためには次のようなポイントを押さえておきましょう。
企業や目的によって適したFAQシステムは異なります。例えば従業員向けの簡易的なFAQであれば、顧客向けよりもデザインにこだわる必要はなく、Excelでの代用も可能です。一方、業務の手順を具体的に共有するのであれば、動画や画像の挿入に対応しているFAQシステムが適しています。
またFAQシステム導入のコストを抑えたいのであれば、無料で利用できるシステムも候補に挙げられます。しかし、無料のFAQシステムは、アカウント数や登録できる質問・回答数などに制限があることが一般的です。
システムを選ぶ上では次のような点も確認しておきましょう。
FAQシステムを選ぶのであれば、他のツールと連携できるのかを確認しましょう。例えばチャットツールと連携できるシステムであれば、従業員からチャットで質問された情報を収集できます。また問い合わせ管理システムや顧客管理システムと連携することで、顧客からの問い合わせを集められます。
使いやすい仕様になっているのかもFAQシステム選定のポイントです。顧客や従業員が使いにくい仕様だと、有人相談窓口に質問が寄せられてしまい、問い合わせ件数が削減できません。操作性に優れたシステムを導入しましょう。
操作性を確認するには、システムツールをお試しできるフリープランの活用がおすすめです。費用が発生しないうちに、どれだけ使いやすいのかを確認しておきましょう。
FAQの運用では定期的なメンテナンスが必要です。従って、メンテナンスしやすいシステムの導入をおすすめします。管理画面が使いやすいシステムであれば、よりスムーズに作業を進められるでしょう。
中には、更新を委託できるサポート体制が整っているシステムもあります。このようなシステムを導入すれば、自社の従業員は本来の業務に注力できます。サポート体制はシステムによって異なるため、事前にどのようなサポート体制なのかを確認しましょう。
FAQやQ&Aでは、あらかじめ目標を設定しておくことがポイントです。例えば、以下のように具体性を持たせるとよいでしょう。
「〇」の部分に具体的な数値を設定することで、メンテナンスの際に目標達成に向けた改善策が見つけやすくなるでしょう。
前述の通り、FAQやQ&Aには定期的なメンテナンスが必要です。FAQやQ&Aを導入しても成果が出ないのであれば、次のような方法でメンテナンスを試みましょう。
利用しやすいFAQやQ&Aにするためには、検索フォームを設置して検索性を高めるのがおすすめです。関連するキーワードや質問を提案するサジェスト機能が備わったシステムであれば、より高い検索性を実現できます。
またFAQ、Q&Aを設定する際は、検索されやすいキーワードを盛り込みましょう。検索されやすいキーワードを盛り込むことで、検索エンジンからの流入も期待できます。
FAQの件数が多い場合は、カテゴリに分けることで利便性が高まります。FAQの利用率が芳しくなければ、カテゴリ構成を変更してみましょう。内容や種類、サービスごとにカテゴリをまとめたり、サービスや商品利用の手順に沿ってカテゴライズしたりするなど、ユーザー目線に立ってカテゴリの構成を変更しましょう。
質問と回答は、誰もが理解できる分かりやすい表現を使うことが重要です。できるだけ専門用語は避け、必要な場合は注釈を付けて説明を加えるようにしましょう。
また回答は端的な文章で記載することも大切です。長い文章は、ユーザーが疑問を解消するまでに時間がかかることがあります。文章が長くなるようであれば箇条書きにしたり別ぺージで説明したりしましょう。
FAQ、Q&Aの管理先は、問い合わせ窓口と一元化することで、よりスムーズに運用できるようになります。管理者がばらばらだと情報管理やメンテナンスがしにくいことがありますが、一元管理すると情報共有が容易になり、業務の効率化が期待できます。
従業員向けのFAQやQ&Aを運用する際は、運用ルールを設けておきましょう。運用ルールが定められていない場合、FAQやQ&Aが活用されず、業務効率化が達成できない可能性があります。担当者の負担を軽減するためにも、疑問点は一度FAQやQ&Aで確認するといった決まりを設けましょう。
また分かりにくい回答を見つけた場合は管理者へ報告する規則を設けておけば、FAQやQ&Aのブラッシュアップにつなげられます。
ここでは、FAQとQ&AのうちFAQの作り方を紹介します。一般的に、次のようなステップで進めます。
最初に掲載したい質問と回答を集めましょう。質問と回答を集めるためには、電話やメール、問い合わせフォームなどの内容を洗い出す必要があります。また顧客や従業員にアンケートを取り、疑問を抽出して、FAQに活用する方法もおすすめです。
加えて社内で商品やサービスを実際に試してみて、生じた質問と回答をFAQに盛り込むのもよいでしょう。
質問と回答を収集したら、FAQに掲載する項目の優先順位付けとカテゴライズを進めていきましょう。
優先順位を分析する際は、ABC分析の活用がおすすめです。ABC分析は、質問の重要度を3つのランクに分けて考える方法です。問い合わせ頻度が特に高い質問をA、問い合わせ頻度が中程度の質問をB、問い合わせ頻度が低い質問をCのグループに分類しましょう。Aに該当する質問はFAQに掲載し、Bに該当する質問は状況に応じてFAQに掲載します。
FAQユーザーの利便性を高めるのであれば、優先順位に加えてカテゴライズも効果的です。ユーザーの立場になり、どのようにカテゴライズすれば分かりやすいかを検討しましょう。
FAQがまとまったらWebサイトに公開します。ただし、FAQを公開したとしてもユーザーの目に付かなければ意味がありません。Webサイトの主なページにFAQへのリンクを設置することが重要です。
なお、Webサイトに公開する際は事前にFAQの内容を確認しましょう。FAQの作成者は問題ないと感じていても、ユーザーが違和感を覚えるケースや、必要な情報が抜け落ちているケースも考えられます。このようなトラブルを避けるために、Webサイト公開前に別の従業員がユーザー目線に立ってFAQをチェックすることをおすすめします。
FAQの設置後は、定期的にデータを分析して改善につなげましょう。例えば次のような項目をチェックするとFAQの成果が出ているのかが判断できます。
定期的にデータを分析して改善を繰り返すことで、よりFAQの精度を高められるでしょう。
FAQやQ&Aを設置したからといって、理想の結果が得られるわけではありません。ここでは次のような失敗例について解説します。
問い合わせ業務に割かれる人件費を減らすためにFAQやQ&Aを設置したにもかかわらず、コストが削減できないケースがあります。要因として考えられるのは次の通りです。
このような原因で問い合わせに割かれる人件費が削減できていないのであれば、FAQやQ&Aのカテゴライズ方法や設置場所を見直してみましょう。例えば、Webサイトの全てのぺージで表示されるグローバルナビゲーションにFAQやQ&Aへのリンクを設置することで、多くのユーザーの目にとまりやすくなります。
FAQやQ&Aの運用や登録に関するルールが曖昧なことで、回答の精度が低くなることがあります。例えば、1つの質問に対して複数の回答が存在している、カテゴライズ漏れが発生しているなどです。
このような失敗を避けるためにも、登録やカテゴリ分けに関するルールを明確にしてから運用を進めましょう。
情報が古いままでは、顧客や従業員は納得のいく答えを得られず、使用頻度が減ってしまいます。情報の更新をスムーズに進めるためには、商品やカテゴリごとに担当者を決めることをおすすめします。担当者が責任を持って定期的に情報を更新する仕組みを整えましょう。
FAQとQ&Aはどちらも質問と回答をまとめたコンテンツです。しかし、FAQはよく寄せられる質問と回答をまとめているのに対して、Q&Aはより網羅的な質問と回答をまとめています。両者をうまく使い分けることで、顧客満足度や業務効率を向上させられるでしょう。
FAQやQ&Aによって顧客満足度、業務効率向上を目指すのであれば、amie AIチャットボットの活用がおすすめです。amieは既存のファイルやデータを学習させるだけで、ユーザーの質問に対応できます。質問を入力すると、内容に沿った複数の回答候補と、回答の関連するデータのサムネイルが出てくるため、ユーザーは知りたい情報を自分で選択できます。ノーコードで情報を学習する上に、AIが優先順位を付けるため、担当者による運用・管理負担を削減できるでしょう。1カ月のトライアル期間も設けているため、FAQ、Q&Aの導入を検討している方はぜひご相談ください。
