RPAでルーチンワークの課題を解決しよう! RPAが得意とする業務や導入のメリットを解説
2025.5.9
Contents
お役立ちコンテンツ
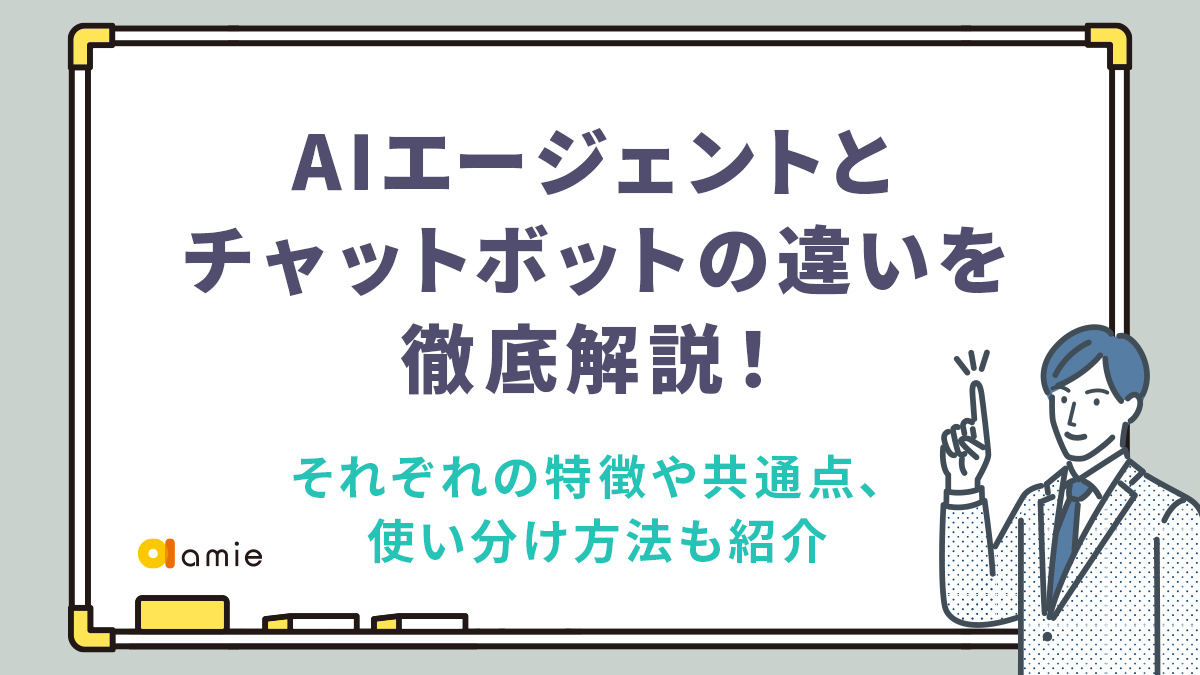
AIの活用が広がる中で、「AIエージェントとチャットボットは何が違うのか」「どちらを導入すべきか」と悩む担当者は少なくありません。特に人事・総務・IT部門では、社内問い合わせ対応の効率化やサポート体制の改善が求められており、最適な仕組みを選ぶことが重要です。
そこで本記事では、両者の違いと共通点を整理し、業務に応じた使い分け方を解説します。AI導入の背景にはDX推進や業務効率化の需要があり、活用シーンは今後ますます拡大していくでしょう。ぜひ参考になさってください。
【この記事を読んで分かること】
目次

AIエージェントとは、自律的に行動し、目標達成や問題解決を支援する生成AIを使ったチャットボットです。大規模言語モデル(LLM)を基盤に、自然言語を理解し、複雑なタスクを分解・遂行できます。従来のチャットボットが「入力に対する回答」を行う受動的な仕組みなのに対し、AIエージェントは「ゴールを設定して自ら行動」できる点が大きな特徴です。
例えば、社員が「来週の会議資料をまとめておいて」と依頼すると、AIエージェントは関連情報を収集し、要点を整理してレポートを自動生成することができます。このように単なる応答にとどまらず、目標達成に向けた一連のプロセスを担えるのが強みです。
AIエージェントはチャットボットの「対話機能」とRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の「処理自動化」を統合した存在といえます。文章生成やプログラミング、スケジュール調整など幅広い業務に対応し、部門横断での活用が期待されています。
AIエージェントは「自律性」「複数ツールを横断」「目標達成に向けて行動する」という3点で従来のツールとは一線を画す存在です。これにより、業務の効率化や付加価値の創出に大きく貢献できるでしょう。
AIエージェントの特徴を整理すると、従来のチャットボットを超える多様な能力が見えてきます。まず大きなポイントは「自律的な行動」です。利用者の指示が細かくなくても、目標達成に必要な手順を推論し、計画を立てて実行できます。
さらに、LLMを活用することで、過去のやり取りやデータを学習しながら最適な判断を下す「推論・学習能力」を備えています。テキストだけでなく、音声・画像・コードを処理するマルチモーダル対応も進んでおり、営業資料の自動作成や画像を用いた製品チェックなど、多彩な活用が可能です。
また、他のシステムやエージェントとの連携も得意です。例えば、スケジュール管理ツールやメールシステムと連携し、会議設定から通知まで一気通貫で行えます。さらに文脈や意図を理解し、過去の履歴を記憶する機能があるため、利用者ごとにパーソナライズされた提案を行うこともできます。
従来のチャットボットがFAQ対応など限定的な場面で活躍してきたのに対し、AIエージェントは複雑で非定型な業務を支援できる点が強みです。例えば営業部門では顧客データを基にした提案書の作成、総務では社内申請の自動処理、IT部門ではログ分析や不具合の一次対応など、多様なシーンで導入効果を発揮します。
将来的には、複数のAIエージェントが協働し、業務全体をオーケストレーションする仕組みへと進化することが期待されています。
AIエージェントにはさまざまな種類が存在し、目的や利用シーンに応じて選ばれています。研究開発向けから商用サービスまで幅広く展開されている点が特徴です。
代表的な例を挙げると、AgentGPTはWeb上で動作する自律型エージェントで、タスクを自ら分解し実行する仕組みを備えています。BabyAGIは研究コミュニティで注目された自律型エージェントの原型で、タスク生成と優先度管理を組み合わせて行動します。
またAutoGenはマイクロソフトが提唱するマルチエージェントフレームワークで、複数のエージェントが協調して複雑なタスクを解決する設計です。
一方、商用サービスとしてはGitHub Copilotが開発者支援に特化し、コード生成やレビューをサポートしています。Salesforce Agentforceは業務システムに統合されたエージェントで、顧客対応や営業支援を自動化することが可能です。さらに、crewAIのように、データ分析や業務自動化に活用されるプラットフォーム型のエージェントも普及しつつあります。
研究開発系と商用実用系、またオープンソースと商用プロダクトの違いは、柔軟性と安定性のバランスに表れます。今後はマルチエージェント連携や業務横断の自動化に対応する仕組みが主流になっていくと考えられるでしょう。
AIエージェントは、複雑な業務フローを自動化したり、意思決定を支援したりする場面で力を発揮します。例えば営業部門では、顧客データを基にした提案書の自動生成や、見込み客へのフォローアップを自動化することが可能です。これにより営業担当者は戦略的な業務に集中でき、リソース配分の最適化にもつながります。
社内業務においては、会議の議事録作成や要約、各種申請業務の処理をAIエージェントに任せるケースが増えています。情報ソースを横断的に統合し、必要な情報を自律的に提示することで、社員の検索負担を大幅に削減できるでしょう。さらに、ITサポート分野ではログ分析や不具合検知の一次対応を担い、担当者の負担軽減にも寄与しています。
カスタマーサポートでもAIエージェントは有効です。顧客の問い合わせに応答するだけでなく、CRMと連携して過去のやり取りを踏まえた回答を提示できます。これにより、24時間体制で一貫した対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
成功のポイントとしては、社内データと連携した適切なチューニング、セキュリティやプライバシーの確保が挙げられます。導入コストやデータ管理の課題はありますが、得意な領域を明確にすれば、DX推進や人的リソースの補完に大きな効果を発揮します。

チャットボットとは「チャット(会話)」と「ロボット(自動化)」を組み合わせた言葉で、ユーザーからの入力に応じて自動的に応答する仕組みを指します。テキストや音声で入力された質問を自然言語処理で理解し、適切な回答を返すのが基本的な機能です。
代表的な活用例はカスタマーサポートで、営業時間外でも24時間対応できる点が強みです。顧客からのよくある質問に即時対応することで、待ち時間を減らし、担当者の負担を軽減できます。さらに、CRMやFAQデータベースと連携すれば、より正確で一貫性のある情報提供が可能です。
チャットボットには大きく分けて「ルールベース型」と「AI型」があります。ルールベース型はあらかじめ設定されたシナリオに従って応答するため、回答精度が安定している一方、想定外の質問には対応できません。AI型は機械学習や自然言語処理を用いて柔軟な応答ができ、利用者とのやり取りを通じて精度を高める特徴があります。
歴史的に見ると、初期のチャットボットは簡単なキーワードマッチングによる単純な応答が中心でした。しかし近年はAI技術の進歩により、顧客の意図を理解し、文脈に沿った自然な対話を実現できるようになっています。企業の導入メリットは効率化や人件費削減だけでなく、顧客満足度の向上にも直結します。
なお、チャットボットとAIエージェントの違いについては次の章で詳しく触れます。まずはチャットボットが持つ基本的な役割を理解しておくことが重要です。
チャットボットの特徴は、定型的な質問応答や簡単なタスクに強いことです。例えばECサイトの注文状況確認や配送日時の変更、よくある問い合わせへの回答などに迅速に対応できます。これにより、顧客は待ち時間を気にせず必要な情報を得られ、企業は人的リソースを削減できます。
もう一つの特徴は「一貫性」です。FAQに基づいた標準的な回答を返すため、担当者による応答のばらつきを防ぎ、ブランドイメージを保てます。シナリオ設計に沿って動作するため、誤情報やハルシネーションが起きにくい点も安心材料です。
費用対効果の高さも魅力です。クラウドサービスとして提供されるチャットボットは初期コストが比較的低く、中小企業でも導入しやすい仕組みになっています。さらに、既存のFAQデータやCRMと統合することで、顧客ごとの履歴を踏まえた回答も可能になります。
一方で、チャットボットには柔軟な対応や創造的なタスクが苦手という側面もあります。そのため「定型業務の効率化に特化した仕組み」と位置づけるのが適切です。カスタマーサポートやECサイトのように問い合わせ内容がある程度想定できる場面では、非常に高い効果を発揮するでしょう。
チャットボットには大きく分けて「シナリオ型(ルールベース型)」と「AI型(AIベース型)」があります。前者は定型的な対応に強く、後者は柔軟なやり取りに強みを持ちます。企業の導入段階や目的によって選択が異なるため、それぞれの特徴を次で詳しく解説します。
シナリオ型チャットボットは、あらかじめ設定されたシナリオやルールに基づいて応答する仕組みです。入力されたキーワードや選択肢に従い、事前に登録された回答を返します。応答の範囲が明確に定義されているため、企業が意図しない回答を防げる安心感があります。
導入や運用コストが低く、短期間で稼働できる点もメリットです。FAQ対応やコールセンターの補助として導入されるケースが多く、特に問い合わせ内容が定型的な業務に適しています。シナリオを組むだけで稼働できるため、導入初期に選ばれることが多いのも特徴です。
一方で、想定外の質問には対応できず、シナリオを追加・修正する手間が必要となります。柔軟性には限界があるものの、安定した運用と費用対効果の高さから根強い需要があります。最近では、AIと組み合わせた「ハイブリッド型」として進化しており、従来の強みに柔軟性を補う形で活用されるケースも増えています。
AI型チャットボットは、ユーザーの意図をAIが解釈し、柔軟に応答できる仕組みを備えています。大規模言語モデル(LLM)やRAG(検索拡張生成)を活用することで、自然で正確な会話を実現できます。言葉の揺らぎを吸収できるため、多様な表現にも対応可能です。
また、利用を重ねることで対話データを学習し、精度を高められるのも特徴です。例えばカスタマーサポートでは、過去のやり取りを踏まえた回答が可能となり、顧客ごとの状況に合わせた対応ができます。ECサイトでは、商品のおすすめや購入サポートを自然な会話形式で行う事例も増えています。
シナリオ型と比べると柔軟性が高い一方、導入コストや運用管理の複雑さが課題です。誤回答のリスクもゼロではないため、有人対応との組み合わせやルール設計が欠かせません。将来的にはマルチモーダル対応や高度な業務支援が進み、より広範な分野で活用が進むと見込まれています。
チャットボットは幅広い場面で活用されており、業務効率化と顧客体験向上に役立っています。一般的な例としては、顧客対応の自動化やFAQの即時回答、24時間体制での情報提供などが挙げられるでしょう。これにより、顧客は時間を気にせず必要な情報を得られ、担当者の負担も軽減されます。
シナリオ型は特にFAQ応答や簡易的な受付、社内ヘルプデスクなどで力を発揮します。決められた質問が多い業務では、安定した応答と短期間での導入が可能です。
一方、AI型はより複雑なサポートに対応でき、有人オペレーターとの連携も進んでいます。例えば、顧客が問い合わせた内容を要約し、オペレーターに引き継ぐことで対応時間を短縮することが可能です。また、マーケティング分野では顧客の嗜好を分析し、商品提案やキャンペーン案内に活用される事例もあります。
国内外の導入事例では、顧客満足度向上や人手不足解消に寄与した例が報告されています。中小企業では小規模に導入してから徐々に拡張するケースも多く、企業規模や業種を問わず適用される可能性が広がっています。
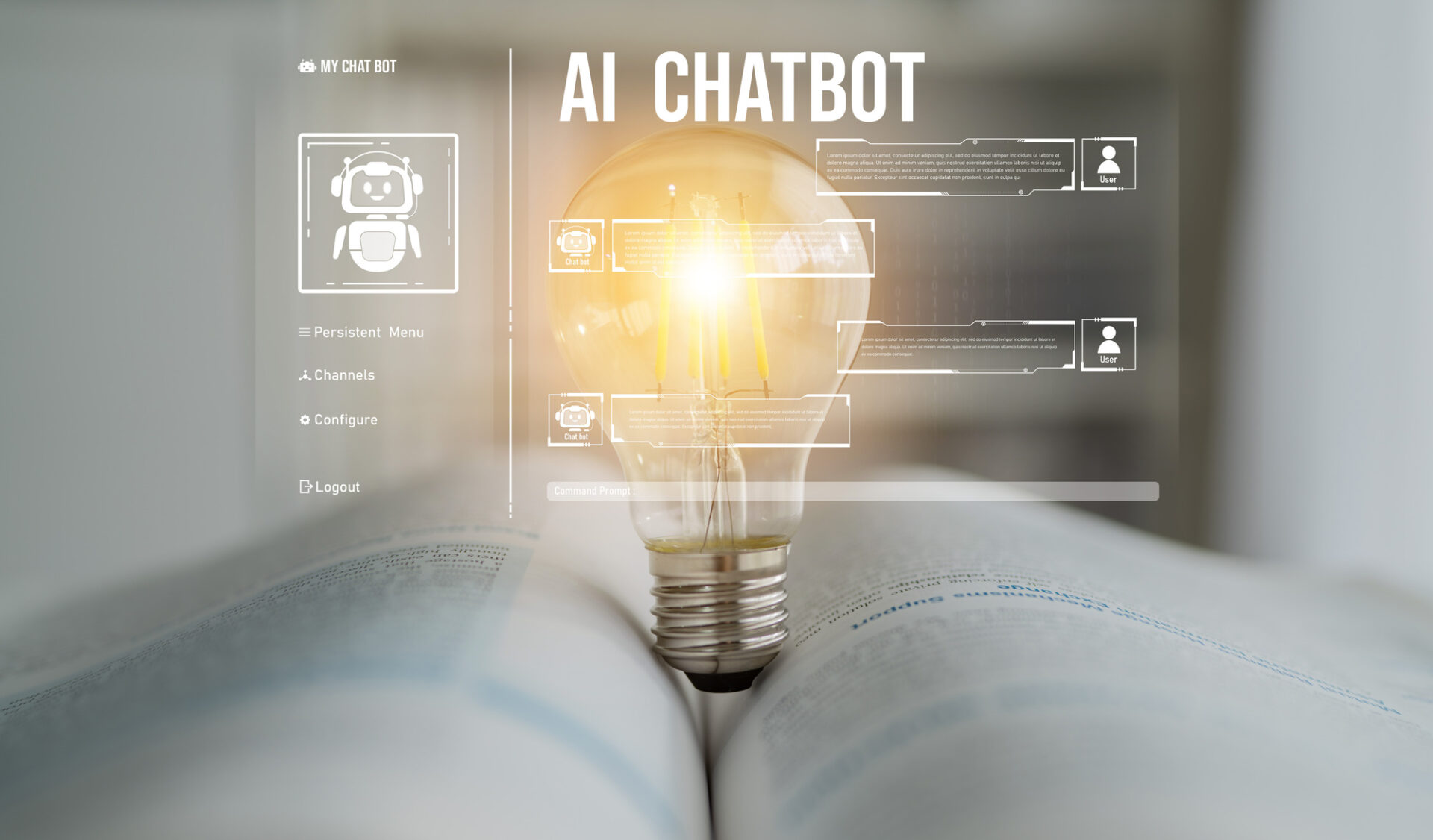
AIエージェントとチャットボットはしばしば混同されますが、得意分野が大きく異なります。チャットボットは、FAQ応答や定型タスクといったシンプルな処理に強みがあります。確実性と一貫性を担保できるため、顧客対応や社内問い合わせの自動化には適しているでしょう。
一方でAIエージェントは、自律的に判断し行動する能力を持ち、複雑なタスクや意思決定支援に強みを発揮します。複数のシステムを横断して情報を統合したり、スケジュール調整やレポート作成などの業務を自律的に進められたりする点が特徴です。
両者を比較すると「単純な処理にはチャットボット」「業務横断的な最適化にはAIエージェント」という構図になります。また、最近では両者を組み合わせたハイブリッド型も登場し、安定した応答と柔軟な処理を両立させる取り組みが進んでいます。
導入に当たっては「どの業務を効率化したいのか」「どの程度の柔軟性が必要か」を明確にすることが、選択を誤らないための重要なポイントです。
違いが注目されがちなAIエージェントとチャットボットですが、実は共通点も多くあります。両者とも自然言語処理(NLP)を活用し、ユーザーからの入力を理解して応答を生成する点は同じです。会話型インターフェースを採用しているため、利用者は直感的に操作できます。
さらに、業務自動化や効率化、コスト削減に寄与する点も共通しています。顧客からの問い合わせ対応を効率化し、24時間体制で応答できるため、顧客満足度を高める効果があります。CRMやFAQデータベースと連携することで、組織全体の情報活用を推進する点も共通要素です。
このように両者は「人手不足の解消」「業務効率化」「顧客満足度の向上」という共通の目的を果たすために導入されており、混同されやすい背景となっています。違いだけでなく共通点を理解することで、自社のニーズに応じた適切な選択につながります。
AIエージェントとチャットボットは、それぞれの強みが異なるため「適材適所」で活用することが大切です。導入目的を明確にし、自社の業務に合った選択をすることで最大の効果を得られます。
AIエージェントを使う場合
チャットボットを使う場合
両者を比較すると「柔軟で高度な業務支援はAIエージェント」「定型業務の効率化にはチャットボット」が基本の使い分けとなります。近年では両者を組み合わせたハイブリッド型も増えており、安定性と柔軟性を両立する運用が可能です。自社の業務課題や導入目的に合わせて選ぶことが、成功の鍵となります。
本記事では、AIエージェントとチャットボットの違いや共通点、使い分けのポイントを解説しました。AIエージェントは自律的に判断・行動し、複雑な業務支援に適した存在です。一方、チャットボットは定型的な質問やシンプルな応答を効率化できる仕組みで、費用対効果に優れています。両者に共通するのは、自然言語処理を活用した会話型インターフェースと、業務効率化や24時間対応を支える基盤技術です。
「amie AIチャットボット」は、社内ドキュメントを活用して回答候補を提示し、サムネイルやPDF形式で分かりやすく情報を提供できる点が特長です。また、単なる「正答率」だけではなく「ユーザーの悩み解決」を重視した設計思想を持ち、AI生成ではなく既存資産から直接回答を抽出する仕組み(RAGとは異なるアプローチ)を採用しています。気になっている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
