RPAはリモートワークでも利用できる? 活用時の課題や解決策を紹介
2025.3.3
Contents
お役立ちコンテンツ

近年、目覚ましい進化を遂げる生成AIですが、その活用が広がるにつれて、大規模言語モデル(LLM)が抱える課題も明らかになってきました。この課題への有効なアプローチとして、今「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」と呼ばれる技術が注目を集めています。RAGは、LLMの弱点であるハルシネーションや情報の鮮度の問題を、外部の知識源を参照することで補い、より信頼性の高い回答生成を可能にする技術です。
本記事では、RAGの中でも特に「G(Generation:生成)」の役割に焦点を当てます。その本質や用いられる技術、そしてAIが「生成」することによって生じる課題や未来の展望を、深く掘り下げて解説します。
目次
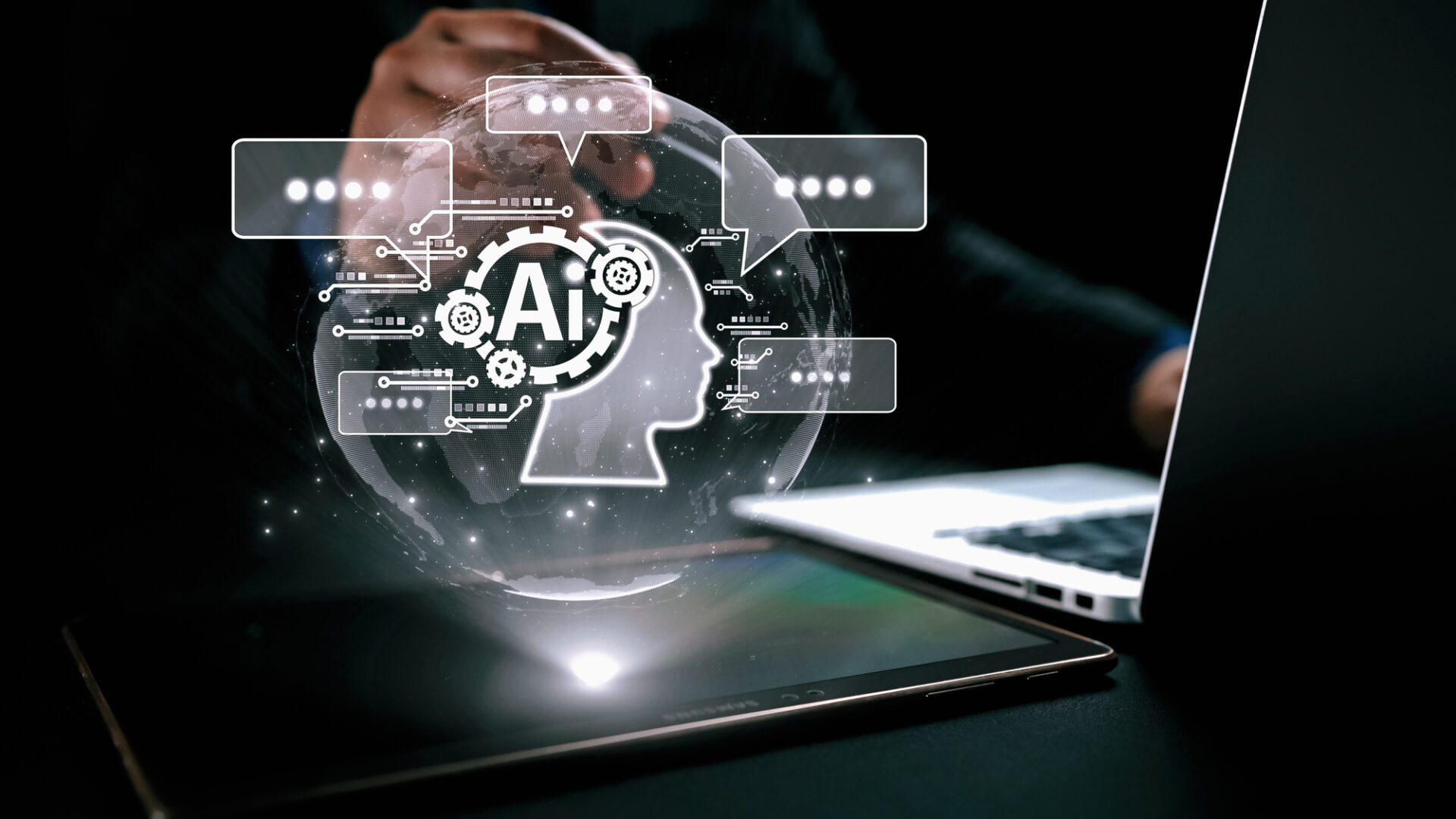
本題である「G(生成)」について理解を深める前に、まずはRAGという技術の全体像を改めて確認しましょう。ここでは、RAGの基本的な定義から、その仕組みやメリットまでを順に解説します。
RAGとは、大規模言語モデル(LLM)が持つ課題を解決するために考案された技術アーキテクチャです。LLMは、時に事実に基づかない情報を生成する「ハルシネーション」を起こしたり、学習データに含まれない最新の情報には対応できなかったりする弱点があります。
RAGは、こうした課題に対し、まず外部の信頼できる知識源から関連情報を「検索(Retrieval)」し、その情報を根拠としてLLMに回答を「生成(Generation)」させることで、より正確で信頼性の高い応答を目指します。
RAGの「R」を担う検索コンポーネントは、社内ドキュメントやデータベースといった外部の知識ベースから、ユーザーの質問に関連性の高い情報を効率的に検索・取得する役割を持ちます。一方、「G」を担う生成コンポーネントは、検索によって得られた情報(コンテキスト)とユーザーの質問文を組み合わせ、LLMなどを用いて自然で分かりやすい文章として回答を生成する役割を担っています。
RAGがユーザーの質問に回答するまでの処理は、一般的に以下の流れで進みます。
RAGは外部の正確な情報を参照するため、LLMのハルシネーションを抑制し、回答の信頼性を高めることができます。また知識ベースを更新することで、常に最新の情報に基づいた回答が可能になります。社内の専門的な文書を知識源とすれば、専門知識を要する問い合わせにも対応可能です。さらに、回答の根拠となった情報源を提示できるため、ユーザーは情報の正しさを自ら確認できます。

RAGの基本的な仕組みは「検索」と「生成」の組み合わせですが、その中でも「G(Generation:生成)」は、単に文章を作り出す以上の役割を担っています。ここでは、生成コンポーネントがRAGシステム全体にどのような付加価値をもたらすのかを、3つの観点から解説します。
RAGにおける「G」が担う役割の一つは、適切な「文脈」を生成することです。検索された情報は、それ単体では単なる事実の断片に過ぎません。「G」は、ユーザーがどのような意図や背景で質問しているのかを汲み取り、その文脈に沿った形で回答を生成します。これにより、無機質な情報の提示ではなく、自然な会話の流れの中で、ユーザーが本当に求めている、価値ある情報として提供されるのです。この文脈生成能力が、RAGシステムの対話体験を豊かなものにします。
RAGシステム全体のパフォーマンスは、「G」の品質に大きく左右されます。たとえ検索コンポーネント(R)がどれだけ的確に関連情報を探し出してきても、最終的な回答を生成する「G」の品質が低ければ、ユーザーの満足度は得られません。生成される回答の自然さや論理的な一貫性、情報の網羅性といった品質は、ユーザー体験(UX)に直接影響を与えます。質の高い「G」があって初めて、RAGは優れた性能を発揮できるのです。
生成AIの信頼性を担保する上でも、「G」は貢献します。優れたRAGシステムでは、「G」が生成した回答が、どの検索結果(情報源)に基づいているのかを明示する機能を備えています。これは「説明可能性(Explainable AI, XAI)」に関連する考え方です。ユーザーは、AIが提示した回答の根拠を自ら辿り、その正しさを検証できます。この透明性が、AIに対するユーザーの信頼を醸成し、企業が説明責任を果たす上で助けとなります。

RAGにおける「G(Generation:生成)」の役割は、近年のAI技術、特に大規模言語モデル(LLM)の目覚ましい進化によって支えられています。ここでは、生成コンポーネントの心臓部であるLLMの基本から、その性能を引き出すための技術、そして目的に合わせたモデルの選び方まで、RAGの「G」を支える裏側の技術を解説します。
RAGの生成モジュールとして広く活用されているのが、大規模言語モデル(LLM)です。LLMは、Transformerアーキテクチャを基盤とし、膨大なテキストデータで「事前学習」を行うことで、人間のような自然な文章生成能力を獲得する仕組みです。RAGにおいては、検索コンポーネントから受け取った情報を基に、このLLMがユーザーへの回答文を生成します。GPTやLlama、GeminiといったさまざまなLLMが存在し、それぞれに特性があるため、目的に応じたモデルの選定がRAGの性能に影響します。
LLMの性能を効果的に引き出す技術が、プロンプトエンジニアリングです。これは、LLMに与える指示や質問(プロンプト)を工夫し、望ましい回答を生成するように誘導する技術を指します。プロンプトには、LLMへの役割指示や、RAGの場合は検索された情報(コンテキスト)、そしてユーザーの質問などが含まれます。回答の形式を指定することも、質の高い出力を得るために有効です。
具体的なテクニックには、いくつかの例を挙げて指示する「Few-shotプロンプティング」や、思考の連鎖を促す「Chain-of-Thought(CoT)プロンプティング」などがあります。RAG特有のプロンプト設計では、検索結果をどのようにコンテキストとしてLLMに的確に伝えるかが、回答精度を左右する鍵となります。
RAGシステムを構築する際は、生成モジュールとなるLLMの選定が必要です。選定基準は、タスクの目的、求められる応答の品質、コスト、処理速度など多岐にわたります。例えば、オープンソースのLLMは自由にカスタマイズできる利点がありますが、商用のAPIは手軽に高性能なモデルを利用できます。
また特定の業界の専門用語や、社内特有の言い回しに対応させるためには、独自のデータでモデルを追加学習させる「ファインチューニング」が有効な手段の一つです。これらの要素を総合的に比較検討し、自社の要件に合ったモデルを選びましょう。
RAGにおける「G(生成)」は、検索結果を基に質の高い回答を生み出す役割を担いますが、そのプロセスにはいくつかの課題が存在します。ここでは、生成段階で発生し得る代表的な4つの課題と、それらを軽減・解決するためのアプローチについて解説します。
RAGはLLMのハルシネーションを抑制する効果が期待できますが、完全には排除できません。検索された情報が不十分、または誤っている場合や、プロンプトの指示があいまいな場合に、LLMが自らの知識で情報を補おうとして事実に基づかない内容を生成してしまうことがあります。
この対策としては、検索コンポーネント(R)の精度を高め、質の高い情報を与えることが第一です。さらに、プロンプトで「情報がない場合は不明と回答する」といった明確な指示を与えたり、生成された内容をチェックするプロセスを導入したりすることも、ハルシネーションの抑制につながります。
検索された複数の情報源の内容が互いに矛盾している場合や、LLMが情報を誤って解釈・統合してしまうことで、生成された回答が不正確になるケースがあります。また生成された回答の文章と、その根拠として提示された情報の内容が一致しないという問題も起こるかもしれません。
対策として、システム内に矛盾を検出するメカニズムを組み込んだり、情報源の信頼性に応じて優先順位を付けたりする方法が考えられます。生成後に、回答と根拠情報を照合するプロセスを強化することも、回答の一貫性を保つ上で有効です。
生成される回答が、必要以上に長文であったり、回りくどい表現で分かりにくかったりする問題も存在します。またユーザーが求めるトーン(丁寧さ、簡潔さ、専門性など)と、実際に生成される文章のトーンがずれてしまうことも、ユーザー体験を損なう一因です。
これらの課題に対しては、プロンプトで「3文以内で簡潔に」といった具体的な長さやスタイルを制御する方法があります。またファインチューニングによって、特定のトーンで話すようにモデルを調整することも可能です。
RAGを実際の業務に適用する際は、そのドメインやユースケースに合わせた「G」のカスタマイズと、品質を管理し続ける難しさがあります。生成される回答が業務要件を満たしているかを継続的に評価し、その品質を維持・向上させるための指標設定やモニタリング体制の構築は、運用上の課題です。
課題を解決するには、複数の回答生成パターンを試すA/Bテストなどを通じて、より良い応答を探求する改善サイクルを確立することが求められます。また人間による定期的なレビューも、品質管理には欠かせません。
RAGシステムにおいて、検索(R)の精度を高めることと並んで、生成(G)の品質を管理・改善することも、活用の成果を左右する要素です。ここでは、なぜ「G」の品質がRAG活用の鍵を握るのか、その理由を3つの側面から解説します。
生成される回答の品質は、さまざまなビジネス成果に影響を与えます。例えば、顧客対応チャットボットの場合、回答が的確か、分かりやすいかどうかが、顧客満足度や問題解決率に反映されます。不正確な回答や不適切な回答は、企業の信頼を損ない、顧客離れや機会損失につながるかもしれません。
また社内向けのナレッジ検索システムでは、従業員が必要な情報を迅速かつ正確に入手できるかが、業務効率や生産性に結びつきます。このように、応答品質はRAGシステムの価値を測る一つの指標となるのです。
ユーザーエクスペリエンス(UX)の観点からも、「G」の品質は大きな意味を持ちます。人間が書いたような自然で分かりやすい応答は、ユーザーがシステムに対して抱くストレスを軽減し、継続的な利用を促します。
また単に情報を提示するだけではなく、ユーザーの質問の意図を正確に汲み取り、期待に応える、あるいはそれを少し超えるような回答を提供できれば、ユーザーの満足度は高まるでしょう。優れたUXは、チャットボットや検索システムが組織に定着するための土台となります。
企業としてAIを活用する以上、出力される内容の一貫性を保ち、ブランドイメージを維持することも重要です。「G」を制御することで、企業としての統一されたメッセージやトーンを維持し、状況によって回答内容が大きくぶれるのを防げます。
例えば、常に丁寧な言葉遣いを徹底させたり、特定の表現を避けさせたりといった制御が考えられます。この一貫性が、ユーザーに安心感を与え、企業のブランド価値を守ることにつながるでしょう。
RAGは、生成AIの進化と共に、現在も活発な研究開発が進められている分野です。その進化は、検索(R)と生成(G)の両面に及び、より高度で信頼性の高いシステムを目指しています。ここでは、RAGとその「G」部分が今後どのように進化していくのか、研究動向や将来の展望について紹介します。
今後のRAGでは、汎用的なLLMをそのまま使うのではなく、特定のドメイン知識や対話スタイルをより深く学習させた、専門性の高いLLMの活用が進むと考えられます。このアプローチは、RAGとファインチューニングを組み合わせるハイブリッドな手法です。
ファインチューニングによってモデル自体の知識や応答スタイルを業務に適合させ、その上でRAGによって最新かつ正確な情報を参照させることで、両者の利点を生かした、より質の高い応答の生成が期待されます。
RAGの基本的な構造そのものも進化を続けています。例えば、キーワード検索とベクトル検索を組み合わせた「ハイブリッド検索」など、より洗練された検索技術の導入が進んでいます。
また一度で回答を終えるのではなく、生成した回答を自ら評価し、必要であれば再度検索と生成を繰り返すことで回答品質を高める反復的なアーキテクチャも研究されています。
これからのRAGでは、検索結果を単なる「参考情報」としてLLMに与えるだけではなく、生成プロセスそのものを、検索結果に基づいてより細かく制御する技術が登場しています。例えば、検索結果に含まれる特定のキーワードや数値を必ず回答に含めるよう指示したり、情報源の信頼度に応じて生成内容のトーンを調整したりといったアプローチです。これにより、AIが自由に文章を作り過ぎることを防ぎ、生成内容の事実性や一貫性を高めることが可能になります。
RAGの応用範囲は、テキスト情報だけにとどまりません。将来的には、画像や音声、動画といった多様な形式の情報を横断的に検索・統合し、それらを基にリッチなコンテンツを生成する「マルチモーダルRAG」への拡張が期待されています。例えば、製品の画像とマニュアルのテキストを組み合わせて、操作説明を生成するような活用が考えられます。
RAGは、外部の知識を検索し、それを基にLLMが回答を「生成」することで、生成AIの信頼性を高める技術です。その心臓部である「G(生成)」は、単に文章を作るだけではなく、情報を統合・解釈し、文脈を生み出すことで、RAGシステム全体の価値に影響を与えます。しかし、AIによる「生成」には、ハルシネーションのリスクが常につきまといます。
情報の正確性が求められる業務におすすめなのが「amie AIチャットボット」です。
「amie AIチャットボット」は、AIが回答を「生成」するのではなく、社内のドキュメントから関連性の高い箇所を「そのまま提示」する検索特化型のアプローチを採用。これにより、ハルシネーションのリスクを原理的に排除し、情報の正確性を担保します。
既存の資料をそのまま活用でき、ユーザー自身が複数の候補から答えを見つけ出せるため、真の自己解決を促進します。AIによる「生成」に頼らない、新しい形のナレッジ活用にご興味があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
