AIの活用で問い合わせ対応を効率化するには?
2025.1.27
Contents
お役立ちコンテンツ
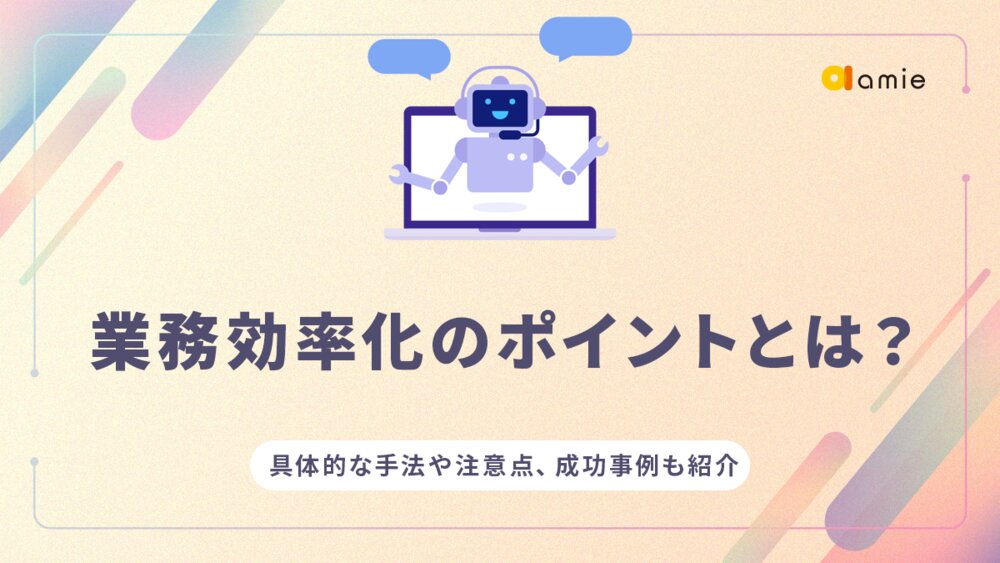
業務効率化は生産性の向上やコストの削減、従業員の働きやすさの向上につながる、企業にとって重要な課題です。しかし、具体的にどのように業務効率化を進めるべきか、また効率化に伴うリスクもあるのではないかと心配している方もいるかもしれません。
本記事では、企業にとっての業務効率化の必要性や具体的な手法、業務効率化に伴う注意点について解説します。また後半では、実際に業務効率化に成功した事例もご紹介するので、業務改善のヒントを探している方は参考にしてください。
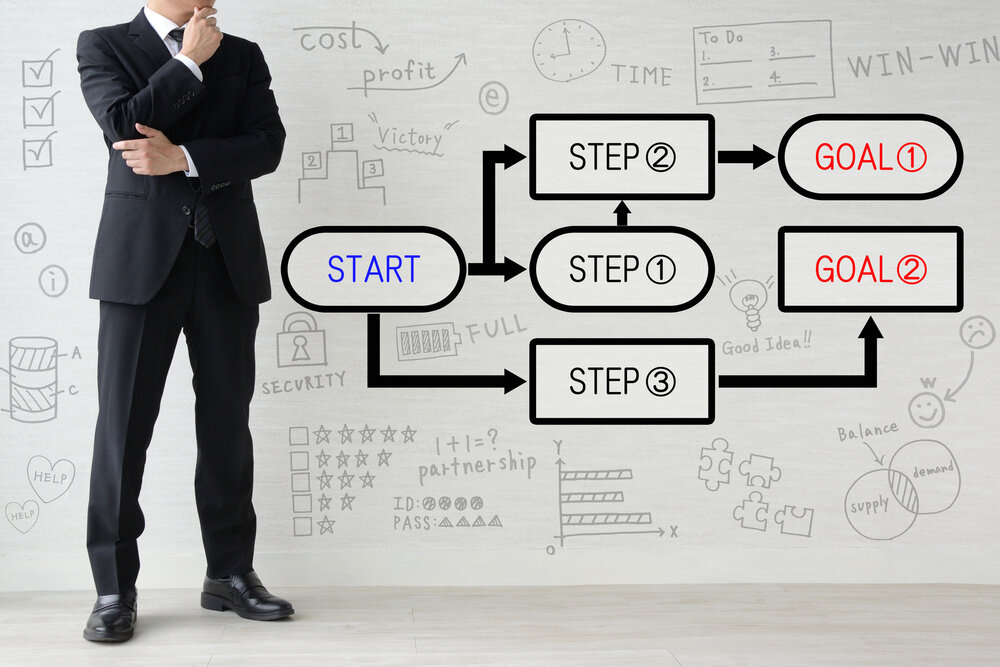
業務効率化とは、業務の中にある「ムリ・ムダ・ムラ」をなくし、業務プロセスを改善することです。
例えば、特定の従業員に過度な負担がかかっていたり、能力以上の仕事を求められていたりする場合は「ムリ」に当たります。また重複している仕事や価値を生み出さない仕事は「ムダ」に、担当者によって作業量や品質にばらつきが出ている場合は「ムラ」に該当します。
このような「ムリ・ムダ・ムラ」を特定して解消することで、より少ないリソース(時間・人員・コスト)で、これまでと同等の成果を上げられるようにすることが、業務効率化の目指すところです。
業務効率化と似た言葉として「生産性向上」がありますが、両者の意味合いは少し異なります。
そもそも生産性とは、投入したリソースに対して、どれだけ多くの成果を得られたかを示す指標です。生産性は「得られた成果÷投入したリソース」という計算式で表されます。そして生産性向上とは、生産性を高めること、またはそのための取り組み全般を指します。
業務効率化は生産性向上を実現するための手段の一つです。業務プロセスを見直し、ムダ・ムリ・ムラを排除することで投入するリソース量を減らし、結果的に生産性向上を目指します。つまり、生産性向上という大きな目標があり、それを達成するための手段として業務効率化があるという関係性です。
例えば、新しい機械を導入して製品の製造量を増やすことは、成果を増やすことで生産性を向上させる方法の一つです。また、会議時間の短縮や作業の自動化といった業務効率化によって、残業時間を減らしつつ売上を維持することも、投入リソースを減らしながら成果量を維持するという意味で、生産性向上の一つの形といえるでしょう。
多くの企業にとって、業務効率化は喫緊の課題となっています。なぜ業務効率化の必要性が高まっているのでしょうか。ここではその要因を説明します。
業務効率化の必要性が高まっている要因の一つに、リモートワークやフレックスタイム制などを代表とする働き方改革の推進があります。
日本は少子高齢化による労働力不足や生産性の低迷が深刻化しています。このような状況を鑑みて、2019年には働き方改革関連法が施行され、長時間労働を是正しつつ生産性を向上させることが国を挙げて推進されるようになりました。
企業は従業員の残業時間を削減しながら、なおかつ生産性を向上させることが求められています。そのため、限られた時間内で成果を出すために業務効率化が不可欠となっているのです。
加えて、リモートワークが普及したことにより、従来の出社を前提とした業務の進め方を見直す必要性が高まっています。リモートワークは、通勤時間が不要になることで従業員がワークライフバランスを整えやすくなるというメリットがある一方、コミュニケーションが不足したり、書面による承認フローが滞ったりするといったデメリットもあります。
従って、チャットツールやオンライン会議システムを導入するなど、リモートワークを前提とした業務効率化のための対策が求められています。
業務効率化は、従業員のエンゲージメント(仕事に対する愛着や主体性)を高めるためにも必要な取り組みです。
業務効率化が成功すれば、常態化していた従業員の残業を減らせる可能性があります。残業が減ることで、従業員の働きやすさが向上するだけでなく、余った時間をおのおののスキルアップや新しい業務のアイデア出しなどに有効活用できるようになります。その結果、仕事への満足度が上がり、離職率の低下といったメリットにつながるでしょう。
さらに、従業員のスキルアップやアイデアがうまく結びつくことで、イノベーションが生まれやすくなり、結果として変化の激しい社会にも柔軟に対応できる組織体制を構築できるでしょう。

具体的に業務効率化はどのように進めていけば良いのでしょうか。ここでは、業務効率化の手法や活用できるツールについて説明します。
業務効率化を始めるに当たりまず取り組むべきことは、現在の業務内容と流れを把握し全体像を見える化することです。フローチャートやプロセスマッピング、業務日誌などを参考に、どの工程に無駄や重複があるのかを明確にしましょう。業務全体を可視化することで、業務の課題点や無駄な作業を特定しやすくなり、不要な業務を削減・統合して効率化を図れます。
またプロジェクト管理ツールやタスク管理ツールを使って、担当者ごとのタスクの進捗をチーム全体で共有するのも良い方法です。タスクを可視化することで、各担当者の作業状況が一目で分かり、管理者はメンバーの抱える仕事量を把握しやすくなります。
特にリモートワーク環境では、進捗が見えにくくなりがちです。ツールを使って進捗を共有することで、都度仕事の分担を見直せるようになり、チーム全体の業務を円滑に進められるでしょう。
繰り返し作業が多い定型的な業務は、RPA(Robotic Process Automation)ツールによる自動化がおすすめです。事前に作業手順を設定しておけば、RPAツールに組み込まれたロボットが自動で作業を進めてくれます。毎日のデータ入力や書類作成などをロボットに任せることで、人が行っていた定型業務の時間を大幅に短縮できるでしょう。
RPAを導入して日々の単純作業を自動化することで、担当者はその業務にかけていた時間をより複雑なタスクやアイデアが求められる業務に使えます。またRPAツールを使うことで、ヒューマンエラーをなくせることもメリットの一つです。
情報共有や意思疎通に時間がかかると、意思決定が遅れて仕事が滞ってしまいます。業務効率化を進めるには、社内コミュニケーションを円滑にすることも重要です。具体的には、チャットツールやオンライン会議システム、社内の情報を蓄積するナレッジ共有ツールといった、社内コミュニケーションツールを積極的に活用しましょう。
また定期的にチームで対話する機会を設けることも大切です。目標やタスクの進捗、困りごとを小まめに共有することで、適度な緊張感を保ちながらも従業員が安心して働ける雰囲気を作れ、モチベーションや生産性の向上へとつながります。
業務の進め方やノウハウをマニュアル化することも、業務効率化のために重要です。それぞれの担当者が持つ知識や業務のこつを整理し、誰でも理解できる手順に落とし込み、ドキュメントにまとめて共有しましょう。
特定の担当者に業務が偏っている状態では、その担当者が不在になった際に業務が止まったり、品質にばらつきが出たりする可能性があります。マニュアルを整備することで、誰が担当しても一定の品質と効率で業務を行えるようになり、新人も早期に戦力化できるでしょう。
さらに、引き継ぎやOJTにかかる手間が減って教育コストを削減できる他、新人が安心して業務を進められ定着率が向上するといった効果も期待できます。
なお、マニュアルは一度作成したら終わりではなく、定期的に見直して改善を重ねることが大切です。業務内容の変更や新たな知見を反映し続けることで、常に効率的に業務を行える状態を維持できます。

業務効率化を進める際には、いくつか注意すべき点もあります。
業務効率化を進める上でまず注意すべき点は、コミュニケーションが希薄になる可能性があることです。効率化を重視するあまり、会議や日常的な会話を極端に減らしたり、対面やチャットで行っていた確認業務を過度に自動化したりすると、従業員同士のコミュニケーションが不足する恐れがあります。
社内コミュニケーションの不足は、人間関係の悪化や従業員のモチベーション低下、ひいては業務効率の低下といったさまざまな問題につながってしまうかもしれません。また上司や同僚との関わりが薄れると、フィードバックやアドバイスを受ける機会が減り、従業員が自身の成長を実感しにくくなるため、仕事へのやりがいを見失ってしまう可能性もあります。従って、適切な効率化と過度な効率化を慎重に見極めることが大切です。
業務効率化を進める上で、業務が単調になり過ぎないように注意が必要です。業務の自動化や効率化が進んだ結果、従業員が担当する業務が単調で退屈なものばかりになってしまうと、仕事への意欲が低下してしまう恐れがあります。業務効率化は従業員のワークライフバランス改善につながる一方で、定型業務ばかりだと従業員が仕事にやりがいを感じにくくなる場合があるのです。
このような事態を防ぐには、業務効率化を進めつつも、従業員が自主性や創造性を発揮できる余地を残すことが重要です。また効率化によって生まれた時間を、スキルアップや新しい挑戦に充てられるように支援するのも良いでしょう。単に無駄を省くだけでなく、実際に現場で働く従業員を中心とした業務改善を心掛けることが大切です。
業務効率化の取り組みは、すぐに効果が出るとは限らない点にも注意が必要です。短期的な結果にこだわり過ぎないようにしましょう。
例えば、新しいシステムを導入した直後は、従業員が操作に慣れていないため、一時的に生産性が低下することがあります。またマニュアルを作成した場合、実際に効果が現れるのは、次に新入社員が入社して以降になるでしょう。
このようなケースで短期的な指標だけを見て効果がないと判断してしまうと、せっかくの改善策を途中で諦めてしまうことになりかねません。業務効率化においては、長期的な視点で業務を見直し、PDCAサイクルを回しながら徐々に改善を重ねていくことが重要です。目先の成果にとらわれず、粘り強く改善を続けることで、最終的には生産性向上や従業員のエンゲージメント向上といった大きな成果につながるでしょう。
実際に企業が業務効率化によって成果を上げた事例をいくつか紹介します。
医薬品・医療機器の卸売を行うA社では、全国に多数ある大型倉庫で在庫管理に使うハンディターミナル端末を運用しており、拠点ごとに離れた大量の端末を一元管理するのに苦労していました。端末にトラブルが発生した際は電話で現場から問い合わせ対応を行っていましたが、電話だけでは現場の状況把握が難しく、数十分対応しても解決できない場合は端末自体を本社へ送付する必要があったのです。
またアプリケーションのアップデートも、端末1台ずつ手作業で行っていたため非常に時間がかかり、端末のセキュリティ管理にも不安を抱えている状況でした。
そこでA社では、MDM(モバイルデバイス管理)を導入。その結果、以下のような点が改善されました。
A社はMDM(モバイルデバイス管理)導入によって業務効率化を実現し、さらに端末紛失時の遠隔操作により、従来懸念されていたセキュリティリスクへの対応も強化できました。
MDM(モバイルデバイス管理)「SOTI MobiControl」の詳細はこちら
フィットネスクラブ運営・用品販売を手掛けるB社では、店舗の売上会計処理に時間がかかり過ぎて顧客を待たせることが多いという課題がありました。また日々の店舗事務処理が煩雑であったため、業務の抜け漏れが発生し事務作業の精度にも問題が生じていました。
そこでB社では、iPadベースのPOSシステムを導入。その結果、以下のような改善が見られました。
またPOSで顧客情報と購入商品のひも付けが可能となったため、購買データの分析結果に基づく販促活動が可能となり、リピート顧客の増加につながっています。
金融系システム開発や業務系システム開発などを行うC社では、社内の総務部や情報システム部門に同じ内容の問い合わせが何度も寄せられ、特定の担当者が日々その対応に追われていました。社内ドキュメントがさまざまな場所に点在し、必要な情報を見つけるのに時間がかかっていたのです。
そこでC社では、社内の問い合わせ対応に「amie AIチャットボット」を導入しました。その結果、以下のような改善が見られました。
問い合わせ対応が減ったことで、問い合わせをする側・受ける側双方が本来の業務に集中できる環境が整い、社内の生産性向上につながりました。
業務効率化を成功させるためには、単に無駄を省くのではなく、適切な手法を選び、継続的な改善を行うことが重要です。業務の見える化やRPA、AIチャットボットの活用など、多様な手法があるため、企業の状況に合わせて適切な方法を選びましょう。
ただし、業務効率化を推し進め過ぎると、コミュニケーション不足やモチベーションの低下につながる場合もあります。今回紹介した成功事例や従業員の意見も参考にしながら業務効率化を実践し、企業の持続的な成長につなげましょう。
業務で必要な情報がすぐに見つからなかったり、社内の問い合わせ対応に時間がかかったりといった課題があるなら、「amie AIチャットボット」の導入がおすすめです。
amieは既存の社内ドキュメントなどを学習し、ユーザーの質問に回答する生成AIを活用したチャットボットツールです。一つの質問に対して、関連性の高い複数の回答を提示してくれるため、ユーザー自身が最適な情報を選べます。
業務効率化をお考えの際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。
