チャットボットのAPI連携で起こる効果とは? メリットや注意点を解説!
2024.9.26
Contents
お役立ちコンテンツ
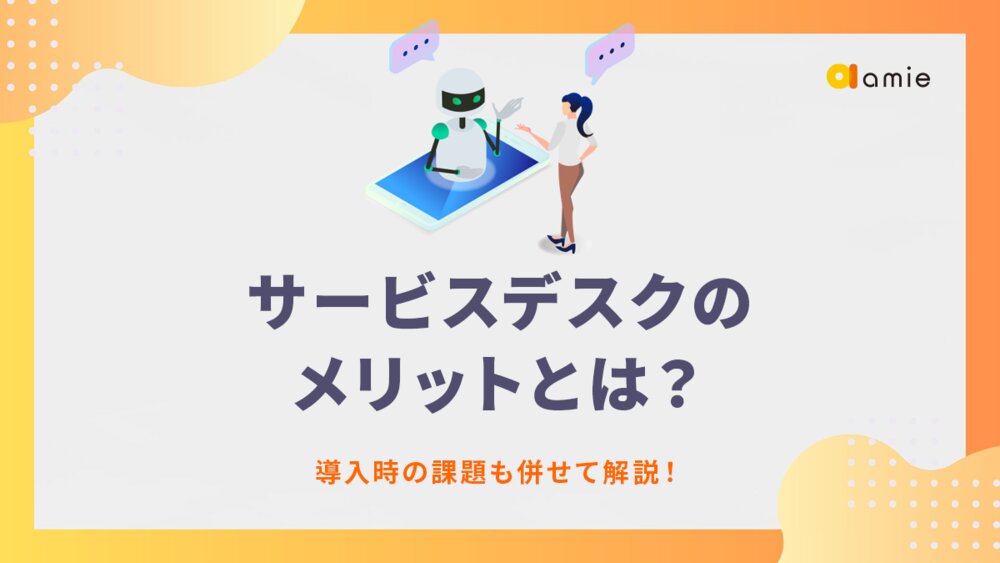
「顧客からの問い合わせ対応に時間がかかってしまい他の業務に集中できない」
「社内の情報共有がスムーズにできていない」
このような課題は、サービスデスクの導入によって解決できるかもしれません。
本記事では、企業がサービスデスクを導入するメリットや、サービスデスクの業務内容、種類について解説します。さらに、導入する際の課題についても併せて解説しますので、問い合わせ対応や情報共有の効率化をお考えの際にはぜひ参考にしてください。

サービスデスクとは、社内外を問わず自社の製品やサービスに関する問い合わせを受け付け、解決に導く業務や部門のことです。顧客やユーザーが困ったときに最初に相談できる窓口として機能し、問い合わせを一元管理することでスムーズな対応を実現します。このような単一の窓口はSPOC(Single Point Of Contact)と呼ばれ、ユーザーはどこに連絡すれば良いか迷うことなく、適切な対応や解決策を得られます。
またサービスデスクは顧客だけでなく社内の問い合わせにも対応し、技術的な質問だけでなく、製品やサービスの使い方、契約内容の確認などを含む総合的な問い合わせを受け付けることも特徴です。さらに、サービスデスクは単に受け身で問い合わせを処理するだけでなく、顧客や社内向けに積極的な情報発信を行い、問題の未然防止や業務効率化にも貢献します。
サービスデスクとヘルプデスクはどちらも問い合わせ対応を行う窓口ですが、その役割や対応範囲に違いがあります。
サービスデスクが社内外からの総合的な問い合わせに対応するのに対し、ヘルプデスクは主に顧客からの技術的な問い合わせに対応する窓口です。例えば、パソコンやソフトウェアの不具合、システムのエラーメッセージ、ネットワーク接続の問題など、IT関連のトラブル対応が中心です。ヘルプデスクは基本的に受動的に問い合わせを受け付け、解決策を提供することが主な役割であり、自ら情報発信を行うことはあまりありません。
つまり、サービスデスクは問い合わせ対応にとどまらず、業務の最適化や情報提供を通じて積極的にサポートを行うのに対し、ヘルプデスクは特定の技術的な問題に特化し、ユーザーからの問い合わせに対応することが主な役割となっています。

サービスデスクの業務は、問い合わせ対応やトラブル解消に加え、情報発信や調査を通じたサービス品質の向上まで幅広く含まれます。具体的には以下のような業務を担い、顧客や社内のサポートを行います。
サービスデスクは、顧客や社内からの問い合わせを一元的に受け付け、適切な対応を行います。具体的には、製品・サービスの使い方に関する質問や契約手続きの案内、システムの操作方法などです。主に電話やメール、Webフォームを介して問い合わせ対応を行いますが、近年ではチャットアプリやAIチャットボットを使って対応を行うケースも見られます。
またサービスデスクでは、問い合わせ内容に応じて即時回答を行う他、専門部署や担当者への対応依頼を行うこともあります。サービスデスクは社外だけでなく社内からの問い合わせにも対応し、他部署の社員からのシステム関連の相談なども受け付けるため、対応する範囲は非常に広範です。しかし、サービスデスクでは対応マニュアルを作成し、その内容に基づいて対応を行うため、どの担当者が対応しても一定の品質を保てます。
製品やサービスの不具合といったインシデントに対応し、迅速な問題解決を図ることもサービスデスクの重要な役割です。インシデントが発生した場合、まずは原因を特定し応急処置を行います。その後、必要に応じて専門部署や技術担当者と連携し、問題解決に向けた進捗管理を行います。
サービスデスクが一元的な窓口となることで、顧客やユーザーが適切な窓口を探し回る必要がなくなり、ストレスが軽減されます。また対応の履歴を記録し、同様のトラブルが発生した際に迅速に対応できるようナレッジを蓄積することも、サービスデスクの重要な業務の一環です。
サービスデスクの業務は、問い合わせへの対応やトラブルの解決にとどまらず、積極的に情報発信を行い顧客や社内業務をサポートします。例えば、新機能やシステムの更新情報をユーザーに案内したり、過去の問い合わせを元にFAQを作成・共有したりします。これによって、同様の問い合わせに対して迅速な対応が可能となり、全体の業務効率が向上します。
さらに、顧客満足度調査を実施しサービスの改善に役立てるといった業務も担当する場合があります。調査結果の分析を通じて顧客のニーズや課題を把握し、関係部署と連携して製品やサービスの改善やFAQの充実を進めることで、顧客満足度をより高められます。
このように、サービスデスクは単なる問い合わせ窓口ではなく、企業全体の業務効率向上や顧客体験の向上を支える重要な役割を担っています。
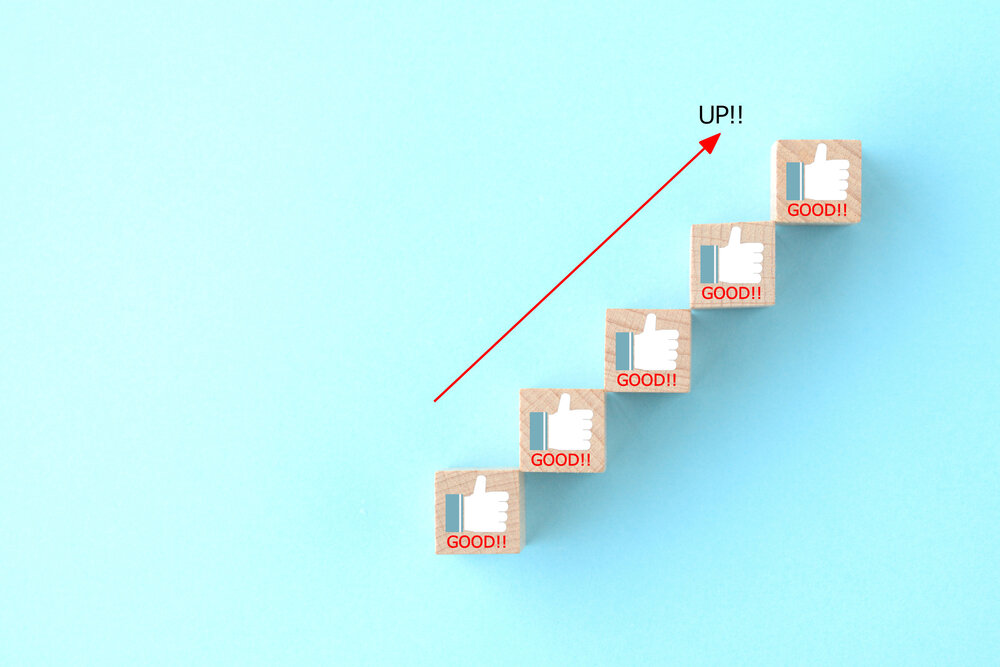
サービスデスクを導入・配置することによって、企業はさまざまなメリットを得られます。ここでは、代表して5つのメリットを紹介します。
サービスデスクを設けることで、顧客からの問い合わせへの対応品質やスピードが上がり、結果として顧客の満足度を高められます。顧客が製品やサービスを使う中でトラブルや疑問が生じた際に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかどうかは、企業の印象を大きく左右します。
従来のような部署ごとの個別対応では、担当者によって回答にばらつきが生じることがありました。一方、サービスデスクでは対応マニュアルを整備し、それに基づいて対応するため、誰が対応しても一貫した正確な回答が可能です。またサービスデスクを導入すれば、問い合わせを一元管理し、適切な担当者へスムーズに振り分けられるため、顧客はよりスムーズに問題を解決できます。
さらに、サービスデスクの体制が整えば、さまざまな問い合わせ方法に対応できるようになります。電話やメール、チャット、Webフォームなど顧客が利用しやすい方法で問い合わせができるようになれば、顧客満足度がより向上するでしょう。特に近年では、AIチャットボットの活用により24時間体制でのサポート提供も実現可能となり、問い合わせ対応がより迅速になっています。
サービスデスクの導入は、業務効率化にも貢献します。問い合わせ窓口を一つにまとめることで、重複対応や対応漏れをなくし、より円滑に業務を進められます。
従来のような各部署による個別対応では、同じ問い合わせが複数の部署に寄せられたり、対応状況があいまいになったりする場合があります。サービスデスクでは、問い合わせをまとめて管理することで、担当者間の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また従来は各部署で行っていた問い合わせ対応に時間が取られなくなることで、よりコア業務に集中できるようになります。
さらに、対応履歴のデータを分析することで業務上の課題を明確にし、継続的な業務改善が可能です。例えば、特定の問題に関する問い合わせが多い場合、製品やサービスの仕様を見直すことで根本的な問題解決を図れます。このように、サービスデスクは単なる問い合わせ対応窓口にとどまらず、業務効率化を促進するというメリットもあります。
サービスデスクは、企業のITインフラの安定稼働にも役立ちます。
ITインフラの故障が業務の継続に大きく影響する企業では、トラブル時の迅速な対応が不可欠です。サービスデスクを通じて、インシデント管理(ITサービスにおける障害やトラブルの管理)を強化することで、システム障害が発生した際の初期対応を素早く行えます。
例えば、問題が起きた際に担当部署へスムーズに連絡できる仕組みを整えることで、復旧までの時間を短縮できます。また過去のインシデント対応履歴を記録し、再発防止策を講じることで、同様のトラブルを事前に防ぐことも可能です。
安定したITインフラの運用は、業務の効率化やセキュリティ対策の強化にもつながります。サービスデスクを設置することで、システムトラブルによる業務の停止をできる限り減らし、安定した経営を実現できるでしょう。
企業において、特定の担当者に業務が集中してしまう「属人化」は大きな課題の一つです。特定の社員が持つノウハウや知識に依存していると、その社員が退職や異動をした際に業務が滞るリスクが高まります。また業務が属人化していると、新しく担当する人が一からスキルや知識をキャッチアップする必要があり、引き継ぎがスムーズに進まないことも少なくありません。
サービスデスクを設置することで、問い合わせを一元管理し、対応履歴や解決策がナレッジとして蓄積されるようになります。これにより、特定の担当者に依存することなく誰でも同じ水準の対応ができるようになります。さらに、ナレッジ共有が進むことで新しい担当者でも過去の対応履歴を参考にしながら業務に対応できるようになり、教育・研修の負担を軽減することにもつながります。
またサービスデスクがあることで、問い合わせの管理がシステム化され、進捗状況をリアルタイムで把握できるようになります。これにより、対応の抜け漏れを防ぐとともに業務の透明性を確保しやすくなります。特定の社員だけが業務を把握している状態ではなく、チーム全体で共有できる仕組みを整えることが、安定したサポート体制を構築する上で重要なポイントとなります。
企業が市場で競争力を維持・強化するには、製品やサービスの品質を高めることが不可欠です。そのためには顧客の声をきちんと把握し、それを改善に役立てていくことが大切になります。サービスデスクは、顧客からの問い合わせやご意見をまとめて管理できるため、顧客のニーズや課題を把握しやすくなります。これにより、どのような点が不満や問題として多く挙げられているのかを分析し、製品やサービスの改善に反映しやすくなります。
またサービスデスクを通して、顧客が困った際に迅速かつ的確なサポートを行うことは、製品やサービスの評価を高めることにもつながります。例えば、問い合わせに対してスムーズに対応できることで、顧客は製品やサービスを安心して利用できるようになり、結果としてその製品やサービス、ひいては企業への信頼を高められるでしょう。
サービスデスクは、設置場所や運用方法によっていくつかの種類に分けられます。ここでは、サービスデスクの主な種類とそれぞれの特徴について説明します。
ローカルサービスデスクは、各拠点のオフィス内などに設置されるサービスデスクです。公式Webサイト上に一次窓口が設置される場合もあります。オフィス内に設置される場合は、従業員の対面でのサポートが可能であり、トラブルの解決が迅速に行える点が大きな特徴です。特に、ハードウェアのトラブルやネットワークの問題など現場での対応が必要なケースに強みを発揮します。
しかし、拠点ごとにサービスデスクを設置する必要があるため、人員や設備の維持にコストがかかるというデメリットもあります。また基本的に各拠点の営業時間内でしか対応できないため、24時間対応が求められる企業には不向きです。とはいえ、直接的なサポートを求めるユーザーにとっては安心感があり、特に小規模な組織やオフィス単位のサポートでは有効な手段となります。
中央サービスデスクは、企業全体の問い合わせ対応を1カ所に集約し、全てのユーザーに対応する形態のサービスデスクです。拠点ごとにサービスデスクを設置するのではなく、一つのサービスデスクから全てのサポートを提供するため、運用コストを削減しつつサポートの品質を統一できるというメリットがあります。
ただし、全ての問い合わせが一つのサービスデスクに集まるため、対応が集中すると待ち時間が長くなる可能性があります。また各地域・拠点の特有のトラブルなどには対応が難しくなる場合もあります。それでも、効率的な運用を重視する大企業や、多くの拠点を持つ企業にとっては、非常に有効なサービスデスクの形態といえます。
バーチャルサービスデスクは、物理的な拠点を持たずクラウド技術やリモートアクセスを活用してサービスを提供する形態のサービスデスクです。従来のサービスデスクとは異なり、世界中のどこからでもサポートが可能であり、特定のオフィスに依存せずに運用できる点が特徴です。
さらに、物理的な設備や人件費を抑えられるためコスト削減にもつながります。ただし、完全にリモートでの対応となるため、インターネット環境に依存する点がデメリットです。特定の地域や拠点において、ネットワーク障害が発生するとサポートが困難になる場合があります。また対面でのサポートがないため、ユーザーによっては安心感に欠けると感じることもあります。
フォロー・ザ・サンとは、世界各地にある複数の拠点がそれぞれの時間帯に合わせて交代で対応することで、24時間365日サポートを提供するサービスデスクの形態です。日本やアメリカ、ヨーロッパなど、異なるタイムゾーンに位置するチームが順番に業務を引き継ぎながら対応することで、常にサポートを受けられる体制を構築します。
この方式では、一つの拠点に負担が集中することなく業務を効率的に分散できるため、グローバル展開している企業に適しています。しかし、拠点間の引き継ぎがうまくいかないと対応が遅れたり、情報が食い違ったりする可能性があります。また言語や文化の違いがコミュニケーションに影響を与える場合があるため、事前にしっかりと管理体制を構築しておく必要があります。
それでも、グローバル企業にとっては時差による対応の遅れを防ぎ、迅速なサポートを実現できる理想的なサービスデスクの形態といえるでしょう。
サービスデスクを導入・運用するに当たっては、事前に考慮すべき課題も存在します。ここでは適切な人材育成、システムの導入と運用コスト、多岐にわたる業務の管理体制構築という3つの観点から主な課題を整理します。
サービスデスクの運用には、製品やサービスに関する知識と、顧客対応スキルを兼ね備えた人材が不可欠です。しかしながら、適した人材を見つけるのは容易ではなく、特に高度な専門知識が求められる製品やサービスを取り扱う場合、採用はさらに難しくなります。
また採用後も業務をキャッチアップできるよう、教育や研修を実施する必要があるため、時間とコストがかかります。加えて、サービスデスクの業務は多岐にわたるため、担当者によってスキルに差が生じることも課題です。従って、継続的なスキルアップを支援し、効率的に知識を共有できる仕組みを構築することが重要となります。
サービスデスクの体制を構築する際には、多くの場合サービスデスクツールも同時に導入することになります。サービスデスクツールを導入することで業務効率化が期待できますが、サービス選定や導入作業にかかる手間や、初期費用・運用コストについては押さえておかなければなりません。
すでに何かしらの業務システムを利用している場合には、それらのシステムからのデータ引き継ぎや連携作業が必要となります。こうした点を考慮の上で、自社の規模や状況に合ったツールを慎重に選び、導入後の運用フローを想定しておくことが重要です。
前述の通り、サービスデスクの業務範囲は非常に広いため、適切な管理体制を整えることが不可欠です。問い合わせ対応の流れや各担当者へ引き継ぎする際のルール、ナレッジの蓄積方法などを整備しておかないと、せっかくサービスデスクを設置してもスムーズに運用できず、その場しのぎの対応になってしまう恐れがあります。
このような事態を避けるためには、サービスデスクの業務の流れや各種ルールを文書化しておくことが有効です。対応に迷った際はあらかじめ作成しておいた資料を参照するという意識をメンバー全員が持つことで、統制の取れた管理体制を構築できるでしょう。
サービスデスクを導入することで、顧客満足度の向上や業務効率化、ITインフラの運用安定などさまざまなメリットが期待できます。さらに、業務の属人化を防げたり、製品・サービスの競争力を高めるために役立ったりすることもサービスデスクを導入する利点です。
本記事でご紹介したサービスデスクの種類や課題も踏まえつつ、企業のニーズに合った形での導入を検討してください。
問い合わせ業務の効率化には「amie AIチャットボット」の活用もおすすめです。
amie AIチャットボットは、社内の既存ドキュメントやWebサイトの情報を活用し、問い合わせ対応を自動化する生成AIを活用したツールです。
回答はサムネイル付きで複数提示され、直感的に情報を選択できます。またSlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスツールとも連携し、業務効率化を支援します。 AIチャットボットを活用した業務効率化をお考えの際には、ぜひお問い合わせください。
