チャットボットを自治体で導入するには?メリットや導入事例・注意点を紹介
2024.9.26
Contents
お役立ちコンテンツ

ITサービスの運用における問い合わせ対応の遅れやトラブルの長期化は、業務の停滞や顧客満足度の低下を引き起こす可能性があります。このような課題を解決できるのが、ITILに沿ったサービスデスクの導入です。
本時では、サービスデスクとITILの関係性や基本概念、効果的な運用のためのポイント、成功事例を解説します。
目次

ITサービスの品質向上において、サービスデスクとITILは密接な関係にあります。まずは、以下でITILの概念やサービスデスクの役割、2つの関係性を理解しましょう。
ITIL(Information Technology Infrastructure Library)とは、ITサービスマネジメントの成功事例をまとめたガイドラインのことです。ITサービスを導入する際のフレームワークとして認知されており、運用に必要な知識を測る試験にも採用されています。
ITサービスマネジメント(Information Technology Service Management)とは、ITサービスを利用するユーザーが快適に作業できるように業務体制を継続的に見直すことです。
ITILに従ってのITサービスの導入を検討すれば、業務フローに潜んでいる課題が何なのか、今後起こる可能性が高いトラブルなどを洗い出すことが可能です。そして洗い出した課題やトラブルに適した対策を講じ、より質の高いサービスマネジメントを構築できます。
ITILは時代の変化に合わせて進化を続けており、2025年3月時点での最新版は2019年にリリースされたTIL4です。以前のバージョンのITIL3では、サービスライフサイクル(サービスを安定かつ継続的に提供する考え方)を中心に構成されていました。
一方、ITIL4ではサービス提供者と顧客が一体となって価値を共に生み出す「サービスバリューチェーン」が重視されています。これまでの体系的なフローから、顧客のニーズや状況の変化に合わせて価値を創出していく考え方にシフトチェンジされました。
またITIL3では「プロセスと機能」といった枠組みが活用されていましたが、ITIL4では「34のマネジメントプラクティス」が新たに設けられています。
34のマネジメントプラクティスは、一般管理プラクティス・サービス管理プラクティス・技術管理プラクティスの3つに分類されます。詳細は、以下の通りです。
| カテゴリー | 概要 | 具体的な管理・活動 |
|---|---|---|
| 一般管理プラクティス | 組織やビジネスの運営や戦略に関わる管理 14項目に分けられる |
・アーキテクチャ管理 ・情報セキュリティ管理 ・ナレッジ管理 ・測定および報告 ・戦略管理 ・継続的改善 ・リスク管理 ・情報セキュリティ管理 ・要員およびタレント管理 ・事業関係管理 ・プロジェクト管理 ・ポートフォリオ管理 ・組織変更の管理 ・サプライヤ管理 |
| サービス管理プラクティス | ITサービスの品質向上のために実施する管理 17項目に分けられる |
・可用性管理 ・キャパシティおよびパフォーマンス管理 ・インシデント管理 ・事業分析 ・IT資産管理 ・モニタリングおよびイベント管理 ・問題管理 ・リリース管理 ・サービスカタログ管理 ・変更実現 ・サービス継続性管理 ・サービス構成管理 ・サービスデザイン ・サービスデスク ・サービスレベル管理 ・サービス要求管理 ・サービス妥当性確認およびテスト |
| 技術管理プラクティス | ソフトウェアの開発やインフラ管理などの技術的な管理や運営 3種類に分けられる |
・インフラストラクチャおよびプラットフォーム管理 ・ソフトウェア開発および管理 ・展開管理 |
このように、ITIL4は従来の決められた手順に沿ってプロセスを管理するのではなく、状況に応じて柔軟に上記のプラクティスをかけ合わせていく考え方です。
ITILとサービスデスクは、企業や組織の業務効率化において深く結び付いています。
サービスデスクとは、ITILにおいてユーザーと企業のシステム部門をつなぐ窓口です。ITサービスに関する問い合わせやトラブルを一元的に受け付け、解決へ導く役割を持つ部門またはシステムを指しています。
具体的には、企業のIT部門やカスタマーサポート部門に配置され、ITサービスをスムーズに運用するための中心的な役割を果たしています。ユーザーが抱える課題や要望を解決することで、顧客の満足度や社内の業務体制などが改善される仕組みです。
例えば「社内の業務システムが突然動かなくなった」と問い合わせがあった場合、一時的な解決策を迅速に提供します。顧客の問題を解決へ導くことで、顧客満足度向上が期待できるだけではなく、何が原因で問題が起こっていたのかも明らかになります。
結果として、企業のITサービスの品質が向上してITIL成功につながるといった流れです。
サービスデスクとよく似た言葉に「ヘルプデスク」がありますが、2つはそれぞれ業務範囲や解決する目的が異なります。
サービスデスクは、ITサービス関係のトラブル対応だけではなく、企業が提供するサービス全体の管理や改善にも寄与するシステムです。対してヘルプデスクは、主にユーザーの短期的な困りごとを解決する窓口になります。
例えば「社内システムにログインできない」という質問に対して、ヘルプデスクはパスワードをリセットしてログインできるように対応するイメージです。
サービスデスクは、ヘルプデスクよりも包括的なITサポートを行う部門で、ヘルプデスクは特定の短期的な問題を解決する部門と捉えると良いでしょう。どちらも業務効率化や顧客満足度向上のためになくてはならないものです。
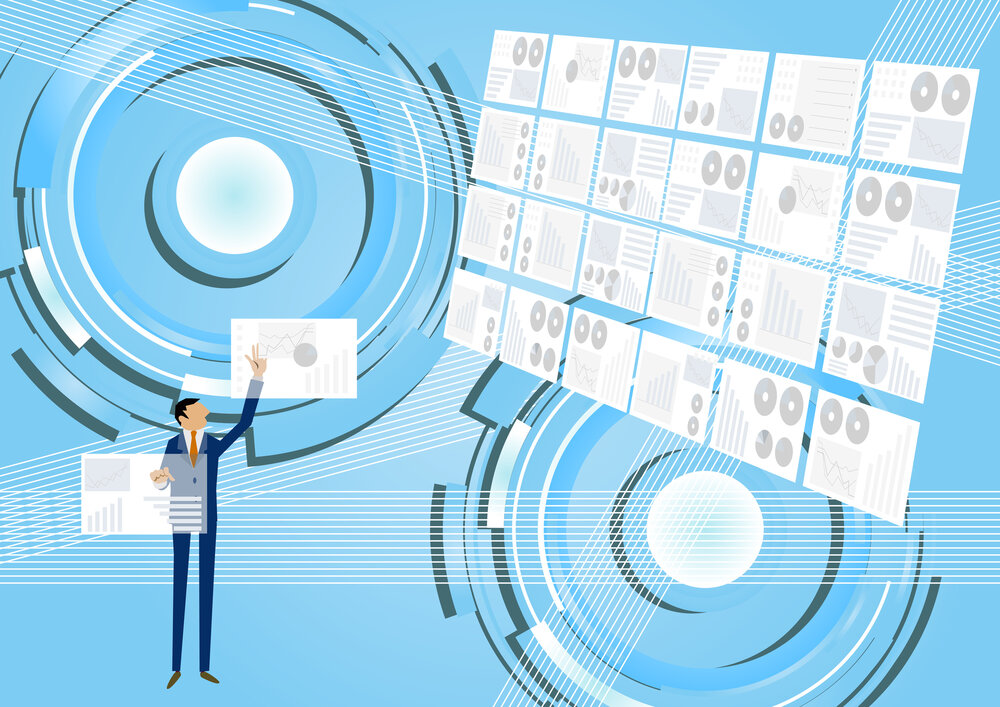
サービスデスクの主な機能は、以下の3つです。
サービスデスクの主な機能の一つが、インシデント管理です。インシデント管理とは、ITサービスに発生した障害やトラブルを迅速に解決し、業務への影響を抑えるための管理です。
インシデントの例は「システムがダウンした」「アプリが起動しない」「インターネットに接続できない」などが挙げられます。これらの問題は社内だけではなく顧客にも影響を及ぼすため、早めの原因追究と復旧が必要です。
例えば、自社のECサイトでサーバーがダウンすると、顧客が一定の時間商品を購入できなくなり、売上がゼロになってしまう可能性があります。そのため、サーバーダウンの原因を特定し、問題なく使用できるまで復旧作業を継続します。
また問題解決までのステップでまず実施するのが、インシデントの検知です。検知後は、トラブルの影響範囲や緊急度を考慮した上で優先順位を決定します。その後、迅速な復旧が必要だと判断した場合、システムの運用担当者に連絡して不具合を修正する流れになります。
サービスデスクは、問題解決の役割も担っています。問題解決とは、繰り返し発生するインシデントの根本原因を特定し、今後同じようなトラブルが起きないように対策を講じるプロセスです。
インシデントは一時的に解決できても、同じ問題が繰り返し発生すると、業務へ影響を及ぼし続けます。問題管理を徹底的に行うことで、トラブルやエラーなどの再発を回避でき、ITサービスの品質が向上する仕組みです。
例えば「特定の業務を行うと、途中で毎回サーバーが落ちてしまう」といった問題に対して、何が原因なのかを追究します。
またインシデント管理との違いは、問題解決の目的が一時的なものか、長期的なものかどうかです。
インシデント管理では「特定のページにログインできない」「サーバーが落ちた」などの一時的なエラーを解決します。一方、問題管理では「特定のページにログインできない理由」や「サーバーが落ちてしまう原因」を探り、必要な改善策を練るフェーズです。
このプロセスを実施することで、根本的な原因が明確になり、ユーザーの利便性や企業への信頼性を長期にわたって維持できます。
ITサービスのインシデントや問題管理だけではなく、変更管理も行います。変更管理とは、ITサービスやシステムに変更を加える際に、システムダウンやウイルス感染などのリスクが起こらないように行う管理のことです。
システム内容を変更する際、以下の作業が発生します。
このような作業でシステムに変更を加える際、適切な手順やリスク管理を行わなければサーバーがダウンして業務が滞る可能性があります。予期せぬトラブルの発生を防ぐためには、変更管理を適切に実行することが重要です。
変更管理を行う際は、まずは何を変更するのか明確化します。その後、優先度やスケジュールなどを設定し、プロセスが実行できるかどうか承認します。承認後は、当初設定したスケジュールや予算に基づいてプロセスを進めていき、レビューで想定の効果が得られているかを確認する流れです。

ITIL準拠のサービスデスクを運用することで、社内の生産性や顧客満足度の向上が期待できます。運用時のポイントは、以下の通りです。
サービスデスクを効率的に運用するには、業務プロセスの標準化を図る必要があります。業務プロセスの標準化とは、社内業務の対応フローを統一し、誰が対応しても一定の品質を維持できるよう業務体制を整えることです。
何をどの順番で、どのようなポイントに注意して作業を行うのか不明なまま導入しても、商品やサービスの質にばらつきが出てしまいます。業務プロセスを標準化し、対応フローを確立すれば、ユーザーの質問やトラブルへ迅速に対応することが可能です。
例えば、インシデントが発生した際は受付から分類、優先度の決定、トラブル解決の実施、クローズといった一連の流れを実施しなければなりません。これらのフローが標準化されていないと、サービスデスクを導入してもインシデントを素早く解決できない可能性があります。
業務を標準化するには、ITILを活用して対応の一貫性を構築すると良いでしょう。ITILに沿って業務フローを定着させることで、各部署のパフォーマンスが上がり、社内の生産性が向上します。
ITサービスの可視化も重要なポイントです。具体的には、サービスデスクの現状やシステムの稼働状況、エラーの発生回数などを明確にしていきます。
可視化ができていなければ、どのような業務にどのくらいの負担がかかっているかが分からず、スムーズに業務改善を実施できない可能性があります。そのため、現状や今後起こり得るインシデントなどの情報を把握しましょう。
またサービスデスクを効率的に運用するには、情報共有や既存ドキュメントの利用も欠かせません。インシデントは、想定した日時に起こるのではなく予期せぬタイミングで発生します。突発的なエラーやシステム障害に対応するには、過去のインシデント対応履歴や手順をドキュメント化し、誰でも参照できる環境を整えることが重要です。
情報共有ができていない場合、担当者ごとに対応方法が異なり、解決までの時間が長引いてしまうことがあります。情報共有が十分にできていれば、突発的なエラーに対して素早く情報を参照できるため、どの担当者であってもスピード感を持って問題解決に取り組めるでしょう。
情報をまとめたドキュメントは、企業のWebサイトやチャットボットに組み込むこともできます。問い合わせ業務が効率化できれば、オペレーター業務負担の改善が可能です。
ITILを活用したサービスデスクツールを活用しながら、ITサービスの可視化を図りましょう。
サービスデスクの効果を引き出すには、ユーザー満足度の向上が欠かせません。
いくら良いサービスデスクを運用していても、問題に対する迅速な回答ができていなければ、ユーザーが使いにくさや対応の遅さに不満を感じてしまいます。そのため、ユーザーの満足度を上げるにはどうしたら良いか、試行錯誤を繰り返す必要があります。
特に重要なのは、サービスデスクの応答率や応答時間です。応答率は、ユーザーからの問い合わせにどれだけ対応できたかを示す指標を指しています。応答率が短いほど、問題解決までのプロセスがスムーズになり、満足度の向上が期待できます。
応答時間は、問い合わせを受けてから実際に回答するまでの時間です。目安としては、インシデントの通知や着信を受けてから30~40秒以内に応答できると良いでしょう。
またユーザー満足度を上げるには、継続的な改善作業が必要です。導入したからといって、すぐに効果が現れるわけではありません。当初設定した目標に近づいているか、業務フローに滞りはないか、同じインシデントが繰り返されていないかを確認することで、成果につながる運用体制が構築されます。PDCAサイクルを回し、定期的に改善作業を行いましょう。
ITIL準拠のサービスデスクを導入するメリットは、以下の通りです。
ITILに準拠したサービスデスクを導入することで、サポート業務の効率化が実現します。
ITILでは、インシデント管理や問題管理、サービス要求の管理などのプロセスが明確に定義されており、ユーザーからの問い合わせ対応を統一された手順で進められるようになっています。そのため、今まで各部署や担当者が個別に対応していた問い合わせをサービスデスクに一元化でき、ITILのフローに沿って対応することが可能です。
さらに、一般管理プラクティスにある「ナレッジ管理」に基づき、ITILに準拠しているサービスデスクには過去のインシデントの対応履歴や修正内容が蓄積されます。情報が集約されていない場合、トラブル発生時の原因追究に時間がかかります。しかし、ITIL準拠のサービスデスクならナレッジが整理されているため、必要な情報をすぐに参照することが可能です。ユーザーの問題解決までの時間を短縮でき、サポート業務を効率化できます。
また情報の一元管理により、他部署で発生したインシデントやエラーにも対応できます。各種トラブルに対処可能な従業員が増えれば、業務の属人化の防止やリピーターの獲得にもつながるでしょう。
ITIL準拠のサービスデスクは、ITサービスの品質向上にも貢献します。
ITILに準拠していないサービスデスクでは、対応の手順や役割が明確に定められていないケースがあり、万が一サーバーダウンなどが発生したときにどう対処すべきか分からなくなりがちです。
一方、ITILに準拠したサービスデスクでは、インシデント管理や変更管理、問題管理などが整備されています。サーバーダウンやシステム障害が発生した際に、誰がどの手順でどのように対応すべきなのかが定義付けられているため、万が一のときでもスムーズな対応が可能です。
特にECサイトやオンライン予約サイトなどは、ダウンタイムが長引くほど顧客満足度が低下する可能性があります。ITILに準拠したサービスデスクを導入すれば、標準化されたプロセスに基づいた迅速な復旧作業が期待でき、顧客満足度向上につながります。
またサービスデスクで集約されたインシデント対応履歴は、ナレッジ管理の一環として社内に蓄積され、将来的なITサービスの品質改善に生かすことが可能です。
ITILに準拠したサービスデスクを導入すると、インシデント発生時の対応スピードが向上します。標準化された手順に従ってトラブル内容を分類し、優先度を判断するため、対応漏れや遅延を回避することが可能です。
システム障害やサービスの不具合が発生した際、適切な一時対応ができなければ、影響が広がって業務の停滞や顧客の不満につながる可能性があります。しかし、ITIL準拠のサービスデスクでインシデントの受付からエスカレーション、解決までの手順が迅速化されれば、スピーディーかつ質の高いトラブル対応を実現できます。
またITILのリスク管理の考え方を活用すれば、潜在的なトラブルを事前に特定することも可能です。問題が起こる前に対策を講じれば、大規模なシステム障害発生などのリスクを大きく軽減できるでしょう。
ITILを活用したサービスデスクを活用することで、ITサービスの品質向上や業務の効率化が可能となります。
ここでは、ITILのフレームワークを活用してサービスデスクの運用を改善し、トラブル対応やインシデント対応の効率化を実現した企業の成功事例を紹介します。
インシデント対応を効率化した企業の成功事例を解説します。
美容業界のある企業では、IT関連の問い合わせ管理にExcelを使用していましたが、情報共有や全体把握の難しさに悩んでいました。そこで、ITIL準拠のサービスマネジメントプラットフォームを導入し、問い合わせ内容の可視化と業務管理の効率化を実現しました。
またCTIとの連携によってインシデント発生時の対応が自動化され、業務の標準化と迅速な対応が可能となった結果、ヘルプデスク業務の品質向上に成功しています。
IT企業では、複数の事業やサービスごとに異なる問い合わせ管理システムを使用しており、1カ月に1,000件近くのインシデントが発生していたとのことです。そこで、ITILをベースにしたクラウド型ITサービス管理ツールを導入し、管理項目の統一や業務プロセスの改善に成功しました。
関連部署とのナレッジ共有が迅速かつスムーズにできるようになり、業務効率化につながっています。
業務の可視化でITサービスの質を向上させた事例を2つ紹介します。
全国に100店舗以上を展開する小売企業は、AIチャットボットamieを導入しました。
主な課題は、本社に各店舗からの問い合わせが頻繁に寄せられ、対応負担が大きかった点です。チャットボットを導入したことで、欲しい情報がすぐに参照できるようになり、本社への問い合わせ件数が大幅に削減されました。
部署別活用事例:店舗から寄せられる質問をチャットボットで自動回答できる仕組みを作成
https://amie-ai.com/industry/industry_example_01/
こちらもAIチャットボットamieを活用した事例です。
あるフィットネスジム運営企業では、フランチャイズ店舗からの問い合わせ対応に多くの時間を要していました。部門ごとに異なるマニュアルを使用していたため、対応の遅れが発生していたとのことです。
そこで、AIチャットボットamieを導入し、マニュアルを一元化しました。結果として必要な情報が一元化され、本社スタッフの業務負担を大きく軽減することに成功しています。
部署別活用事例:フランチャイズ店舗などから本社へ寄せられる問い合わせに対応するために活用
https://amie-ai.com/industry/industry_example_09/
ITIL準拠のサービスデスクは、問い合わせ対応の一元化や業務プロセスの標準化を実現し、ITサポートの負担を大幅に軽減します。インシデント管理や問題管理を徹底することで、トラブル対応の迅速化とシステムの安定した運用が可能になります。
ITILを活用したサービスデスクを導入し、ITサポートの最適化とサービス品質向上を目指しましょう。
問い合わせ業務や社内業務の効率化を図りたい企業さまは、ぜひ「amie AIチャットボット」の導入をご検討ください。amieは、既存の社内ドキュメントから正確な回答を提供するチャットボットです。単語検索だけではなく、関連する情報をサムネイル付きで表示するため、ユーザーは必要な情報を直感的に見つけられます。
シナリオ不要で簡単に導入できるため、サービスデスクを通じた業務効率化を検討されている方は、ぜひお問い合わせください。
