FAQとQ&Aとの違いとは? 導入手順や効果を解説
2025.1.30
Contents
お役立ちコンテンツ

企業の成長を支えるためには、生産性を高め、業務を効率化することが不可欠です。しかし、全ての部署に同じ業務改善策を適用できるわけではありません。それぞれの部署が抱える課題に応じて、最適なアプローチを選択する必要があります。
本記事では、業務効率化の概要や各部署の具体的な効率化施策について解説します。部署ごとの特徴を理解し、適切な改善策を取ることで、企業全体の業務効率化につなげましょう。
目次

業務効率化とは、従来の業務の質を維持しながら業務の時間を短縮し、生産性を向上させる取り組みのことです。より具体的には、業務のムリ・ムダ・ムラを削減し、より合理的な業務フローを構築することを指します。
業務効率化が実現すれば、人的・時間的・経済的コストが削減され、従業員の負担を軽減しながら、企業全体の生産性を高めることが可能です。また作業時間が短縮されることで、従業員がより創造的な業務に集中できるようになるでしょう。
業務効率化の最終的な目的は、企業の利益向上にあります。無駄な作業や不必要なプロセスを削減し、限られた時間とリソースを有効活用することで、業績を最大化することが可能です。具体的には、コストの削減や生産性の向上、従業員の負担軽減、顧客満足度の向上といった効果が期待できます。
業務効率化の基本となる考え方の一つに、ムリ・ムダ・ムラの排除があります。
「ムリ」とは、過度な業務負担や非現実的な計画のことです。特定の従業員へ業務が集中し過ぎていたり、高過ぎる目標設定により長時間労働が慢性化したりしている状態を指します。ムリは従業員の疲弊や生産性低下につながりかねません。
「ムラ」は、業務のばらつきや不均一性を意味します。例えば、タスク処理に個人差が大きかったり、業務が標準化されていなかったりする状態などです。業務プロセスにムラがあると、品質の安定が難しくなり、結果として効率が悪化する可能性があります。
「ムダ」は、業務内の不要な作業や非効率な業務フローを指します。例えば、重複した書類作成や手作業でのデータ入力、不要な会議などが代表的です。ムダをなくすことで、時間やコストを削減し、業務効率を向上させることができます。
業務の生産性を高めるためには、これらの「ムリ・ムダ・ムラ」を明確にし、それぞれに対策を取ることが必要です。
では、具体的に業務効率化のためにどのような施策を行えば良いのでしょうか。
業務効率化の施策は、全社共通で適用できるものばかりではなく、各部署の業務内容に応じて異なるアプローチが求められます。
例えば、経理部門では会計ソフトの導入や経費精算のシステム化が効果的ですが、営業部門ではSFAの活用やインサイドセールスの実施が業務効率化につながります。人事部門では採用・人事管理システムの導入が、またカスタマーサポート部門ではAIチャットボットによる問い合わせ対応の自動化が業務効率化に有効でしょう。
このように部署ごとに業務の内容やフローが異なるため、同じツールや施策が全ての部署に適用できるとは限りません。そのため各部署の特性を考慮し、それぞれの業務に適した効率化の方法を検討することが重要です。
そのためには各部署へのヒアリングを行うなどして、実際に業務を行う担当者の視点で改善策を検討すると良いでしょう。

ここでは企業の主な部署ごとの業務効率化の具体策を紹介していきます。
経理部門は企業の財務を管理する重要な部署です。現状、業務の多くを手作業や紙ベースで行っている場合には、業務効率化の余地が大きいといえるでしょう。
表計算ソフトへの手入力が多いと、ヒューマンエラーのリスクが高まります。また紙ベースの経理業務では、書類の処理や印刷に時間がかかる上、書類の保管スペースの確保も必要になります。さらに、インボイス制度や電子帳簿保存法の影響で、証憑書類の管理が複雑になっていることも負担を増やす要因です。
経理部門においては以下のような業務効率化を実施すると良いでしょう。
まず着手していきたいのは、ペーパーレス化です。紙の書類をデジタル化することで、検索や共有が容易になり、保管スペースの削減にもつながります。
例えば、会計ソフトを導入することで帳簿作成や転記作業を自動化できます。さらに、アクセス制限機能を使ってセキュリティを強化することで、情報管理の負担を軽減することが可能です。またクラウド型のツールを利用すれば税制改正にも迅速に対応できるでしょう。
一部の定型的な業務をアウトソーシングすることも、業務負担の軽減につながります。
例えば、記帳代行や経費精算代行、給与計算代行を外部に委託することで、経理部門はより戦略的な業務に集中できます。さらに、外部の税理士に貸借対照表や損益計算書の作成、年末調整を委託するのも良いでしょう。
営業部門では、移動のために時間を取られやすい他、資料作成や報告書作成などの事務作業の負担が大きく、営業担当者がコア業務に集中できないケースがあります。
営業部門においては以下のような業務効率化を実施すると良いでしょう。
インサイドセールスの実施により、電話やメール、チャットを活用して遠隔で顧客にアプローチし、移動時間を削減することで営業活動を効率化できます。
またインサイドセールスとフィールドセールスの担当者を分けるのも有効です。インサイドセールスが見込み顧客の獲得や情報収集を行っておくことで、フィールドセールス担当者の負担が減ったり、よりニーズにマッチした提案を行ったりすることができます。
SFA(営業支援)ツールやCRM(顧客関係管理)ツールの導入も、営業部門の業務効率化に有効です。
SFAツールは、営業活動の記録や顧客データの一元管理、パフォーマンス分析といった機能を備えています。CRMツールは、顧客の基本情報やサービスの利用状況、購買履歴などを一元管理できるツールです。
これらのツールは営業担当者の事務作業の負担を大幅に軽減してくれるため、営業担当者はよりニーズにマッチする提案を考えたり、営業の戦略を練ったりすることに時間を割けるようになるでしょう。
人事部門は採用や社内人事、研修の実施など業務範囲が多岐にわたるため、さまざまな業務効率化が求められます。
人事部門においては以下のような業務効率化を実施すると良いでしょう。
採用管理システムを使うことで、応募者の情報管理、面接日の調整、応募者の傾向分析などを効率的に行えます。その結果、人事担当者は採用戦略を練ることに集中でき、より効果的な採用活動ができるでしょう。
また人事管理システムを導入することで、従業員の情報をまとめて管理し、素早く情報を取得したり更新したりすることが可能になります。これにより業務の負担が減るだけでなく、人事評価の公平性が増し、従業員のエンゲージメントを高めることにもつながります。
eラーニングは、パソコンやタブレット、スマートフォンなどを通して、従業員が研修や社内向けテストを受けられるシステムです。
従来、新入社員への研修を実施するには、講師や会場の手配、日程調整などさまざまな業務が発生していました。eラーニングを活用して研修を行えば、これらの負担を軽減できます。
さらに、従業員の受講状況や成績の管理などもシステム上で行えるため、特に規模の大きい企業においては業務効率化に役立つでしょう。
カスタマーサポート部門では、対応の品質が顧客満足度や企業イメージに影響を与える場合があります。そのため、日頃から業務効率化に取り組み、空いた時間を対応の品質向上のための取り組みに回していくことが重要です。
カスタマーサポート部門においては、以下のような業務効率化を実施すると良いでしょう。
Webサイトなどに記載するFAQを充実させることで、顧客が疑問を自己解決でき、問い合わせ件数を減らせます。
またAIチャットボットを導入すれば、顧客からの問い合わせに24時間対応できるようになり、日中の従業員による対応の負担が軽減するでしょう。
また問い合わせ管理システムの導入もおすすめです。対応状況をリアルタイムで共有し、メールの見落としや対応漏れを防げます。
ナレッジを蓄積・共有する仕組みを作っておくことも、カスタマーサポート部門の業務効率化のために欠かせません。顧客対応履歴などを基に、都度ナレッジを共有することで、担当者ごとの対応のばらつきをなくし、一定水準の対応を提供できます。
また顧客の声を、商品やサービスの開発部門にフィードバックすることも重要です。その場限りの対応を行うだけでなく、実際にサービスや商品の改善につなげることで根本的な解決となり顧客満足度向上に寄与するでしょう。
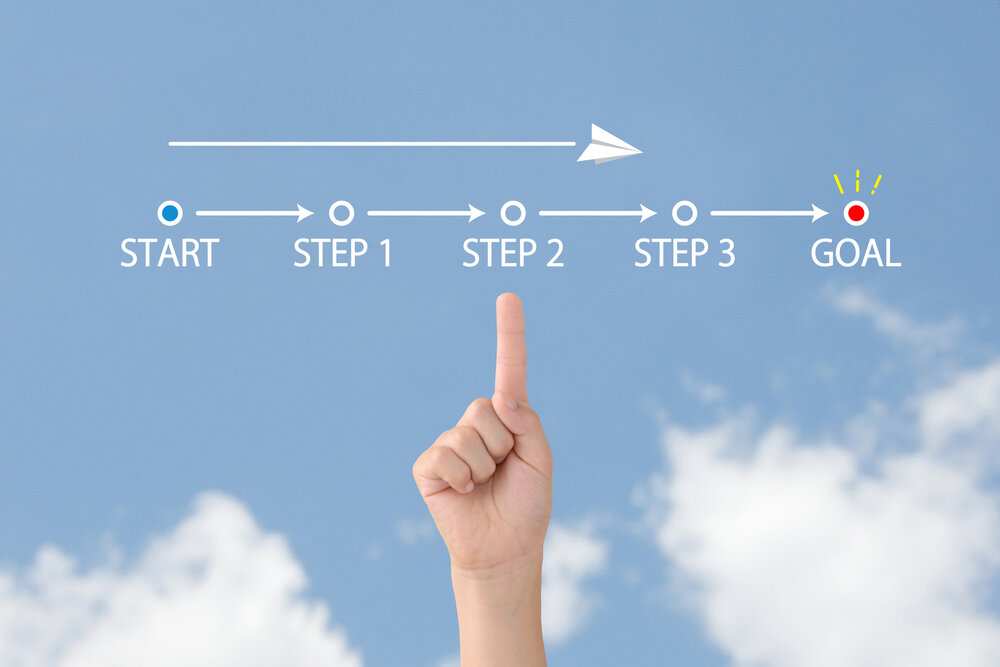
実際に各部署において業務効率化を行う際には、どのような順序で進めていけば良いのでしょうか。ここでは、業務効率化を実施する大まかな流れを解説します。
業務効率化を進めるには、まず現状の業務フローを可視化することが重要です。どのような業務があるのか、誰が担当しているのか、どれくらいの人員が割かれているか、所要時間や工数はどれくらいかといった点を整理し、業務の棚卸しを行います。これにより、不要または重複している業務を特定しやすくなり、どの部分に課題があるのかが明確になります。
業務の洗い出しを行う際には、各部署のメンバーへのヒアリングやアンケートを実施するのがおすすめです。その際、属人化している作業や無駄だと感じる業務なども、併せて答えてもらうのも良いでしょう。
業務の課題が明確になったら、次に適切なツールの選定を行います。ヒアリングやアンケートの内容を基に、より業務効率化につながりそうなツールを選びましょう。
ツールの選定においては、基本機能を比較するだけでなく業界に特化した機能があるかも重要です。また万が一のトラブルに備え、導入後の運用サポートが充実しているかも確認しておくと安心でしょう。
おおよそ導入するツールを絞り込めたら、トライアルなどを利用して実際に使用する現場の担当者の意見を聞くことも大切です。使用感に問題がないかを確かめることで、より業務効率化を実現する可能性を高められます。
新しい業務フローやツールを導入した後は、従業員にそれらを十分に理解してもらうことが重要です。業務変更の内容を丁寧に伝え、必要に応じて研修を行うことで、新しい体制やツールへの移行を円滑に進められます。
従業員が新しいツールや業務フローに対して抵抗感を抱かないよう、導入の目的やメリットを明確に説明し、実際の業務への影響を最小限に抑える工夫をしましょう。「なぜこの業務改善が必要なのか」「どのようなメリットがあるのか」を具体的に説明し、従業員のモチベーションを維持することが大切です。
さらに、適切なサポート体制を整え、必要に応じてフォローアップ研修や勉強会を開催することで、円滑な業務改善を実現できます。
業務効率化に成功した実際の事例を3つご紹介します。自社で業務効率化を実施する際の参考にしてください。
駐車場のスマホ検索システムやキャッシュレス決済システムの開発を手掛けるA社では、契約業務を紙ベースで行っていました。また全国の拠点ごとに契約書の管理体制や進め方が異なっており、本社総務では契約の進捗を正確に把握することが難しく、契約書の検索にも手間がかかっていたのです。
そこで、A社では契約マネジメントシステムを導入し、過去の契約書を含めてデータ化することで、契約業務のプロセスを一元管理できる仕組みを構築しました。
この取り組みにより、各部署の契約書がシステム上で一括管理できるようになり、進捗の把握が容易に。また、過去の契約書もデータベース化されたことで検索性が向上し、業務の効率化が実現しました。
人材サービスを手掛けるB社では、従業員に支給する社用モバイル端末の発注や支払い、紛失時のデータ消去などの管理業務に多くの工数を割いている状態でした。また総務部と情報システム部の両部門で管理していたため、業務の手間が大きくなっていました。
そこでB社では、モバイル端末管理業務を専門の代行会社に委託し、納品、管理、解約、廃棄、請求支払といったライフサイクル全般を一括でアウトソーシングしました。
その結果、モバイル端末の管理業務が効率化され、社内での業務工数が大幅に削減されました。組織をまたいだ管理の負担も軽減され、従業員がより重要な業務に集中できる環境が整いました。
メンタルヘルステック事業やスリープテック事業を手掛けるC社では、営業活動がブラックボックス化していることが課題でした。顧客情報の管理が十分に行われておらず、適切なアプローチができないことで受注機会を逃していました。また営業ノウハウが属人化していたため、業績の安定化が難しい状況でした。
そこでC社は、MA(マーケティングオートメーション)ツールを導入し、顧客情報を一元的に管理する仕組みを構築しました。さらに、メルマガの送付頻度を大幅に増加させることで、潜在顧客への接触機会を増やしました。
その結果、見込み顧客の獲得数が増え、商談件数も大幅に向上しました。営業活動の可視化が進み、営業プロセスの標準化と属人化の解消にもつながりました。
業務効率化は、企業の生産性向上やコスト削減、従業員の負担軽減につながる大切な取り組みです。ただし、全社一律の施策を行うのではなく、各部署の業務内容や課題に応じた適切なアプローチを選択することが成功のポイントとなります。
例えば、経理部門では会計ソフトの導入、営業部門ではSFAやCRMの活用、カスタマーサポートではAIチャットボットの導入など、それぞれの業務特性に合わせた方法を取り入れることが重要です。
業務効率化を進めるためには、まず現状の課題を明確にし、適切なツールや仕組みを導入しながら、従業員がスムーズに活用できる環境を整えることが不可欠です。継続的に改善を重ね、組織全体のパフォーマンス向上を実現しましょう。
業務の情報共有やナレッジ管理を効率化するなら、「amie AIチャットボット」の活用をご検討いただくというのもひとつの手です。
amieは、企業内の既存ドキュメントやWebサイトの情報を活用し、ユーザーの質問に対して関連する資料を提示する、生成AIを活用したチャットボットです。質問すると複数の回答候補が表示され、必要な情報を素早く見つけることが可能になります。
AIを活用した業務効率化を検討される際には、ぜひお気軽にご相談ください。
